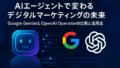大規模言語モデル(LLM)が当たり前になった今、Metaが集中しているのは「次のトークン」ではなく「世界そのもの」を学習するAIです。 本記事では、最新の世界モデル研究(V-JEPA 2 や Code World Model など)の要点を図解イメージで整理しつつ、 デジタルマーケティング担当者にとってどのような意味を持つのかを解説します。
👀イントロダクション:なぜ今「世界モデル」なのか
生成AIやLLMは、テキストや画像をつくるツールとしてすでに広く浸透しています。 しかし、広告運用や顧客体験設計で本当に欲しいのは、「文章そのもの」よりも 「世界の中でユーザーがどう動き、施策がどう効いていくか」を理解し、先回りして動けるAIではないでしょうか。
Meta のチーフAIサイエンティストである Yann LeCun 氏は、LLMだけでは人間レベルの知能には届かないと考え、 物理世界やコードの振る舞いを内部でシミュレーションする「世界モデル」アーキテクチャを長年提唱してきました。 最近の報道では、同氏が世界モデルに注力するために新たな組織を模索していることも伝えられています。
本記事では、Meta が発表した最新論文群(V-JEPA 2・Code World Model など)を「図解イメージ」として整理し、 デジタルマーケティングの現場でどのような応用が見えてくるのかを、マーケター目線でひもといていきます。
大量のテキストからパターンを学び、「もっともありそうな次のトークン」を予測するモデル。 コピーライトや要約、チャットなどが得意。
動画・行動ログ・コード実行などから、 「世界の状態」と「行動の結果」を内部でシミュレーションするモデル。 物理的な直感や、環境の変化を伴うタスクに強みを持つことが期待されています。
この記事で目指すゴール
- 世界モデルの考え方を、マーケターにも分かる言葉に翻訳する
- Meta の最新論文を「図解イメージ」として整理する
- 広告・CRM・プロダクト改善への応用シナリオを描いてみる
🧩概要:世界モデルとは何か、LLMとどう違うのか
世界モデルは、一言でいえば「AIの頭の中にある、世界のミニチュア模型」です。 AIが実世界のすべてをそのまま再現するのではなく、「意思決定に必要な構造だけ」を 小さなシミュレーション空間として持つイメージです。
心理学やロボティクスでは昔から似た概念が議論されていましたが、 深層学習と大規模な動画・行動データの登場によって、 近年「World Models」「World Foundation Models」として再び注目を集めています。
- LLM:言語のパターンを学び、文章として答えを返す
- 世界モデル:世界の状態の変化や因果関係を学び、「このあとどうなるか」を内部でシミュレーションする
- マーケター目線:コピー生成だけでなく、「施策を打つと顧客行動がどう変わりそうか」を試せる可能性がある
従来: 過去データを分析し、その結果をもとに施策を決める(人間が主役)
これから: AIが世界モデルの中で未来のシナリオをシミュレーションし、人間は方針と制約を決める(人とAIの協働)
Meta の最新世界モデル研究の位置づけ
ここからは、世界モデルの中でも特にマーケターが押さえておきたい Meta の2つの論文系統にフォーカスしていきます。
大規模な動画と少量のロボットデータから、 「物体がどう動くか」「どう操作すればよいか」を学ぶ世界モデル。 ロボット制御や物理的な直感に関する研究として位置づけられます。
「世界の状態変化」を内部で予測
コードのテキストだけでなく、 「実行トレース」や「エージェントの開発作業」を学習したモデル。 コードがどう動くかをシミュレーションしながら推論することを目指します。
🎯利点:Metaの世界モデル研究から見える3つのポイント
Meta の世界モデル研究をマーケティング視点で眺めると、次の3つのポイントが見えてきます。
① 動画から学ぶ「物理的直感」:V-JEPA 2 の示す方向性
V-JEPA 2 は、インターネット上の膨大な動画から、物体の動きや人の行動パターンを自己教師ありで学習し、 それをロボット制御や行動予測に活用する世界モデルです。 その後、少量のロボット軌跡データを追加で学習することで、未知の環境でもゼロショットで操作計画ができることが報告されています。
- 大量のラベル付きデータではなく、動画そのものから「世界の動き」を学習
- 「この状況なら、たぶんこう動くはず」という物理的な直感を内部表現として持つ
- 限定された追加データで、新しいタスクに適応できる設計になっている
これは、マーケティングでいえば 「一件一件にラベルを付けずとも、行動ログ全体からユーザーの動き方を学習し、 施策の変更に対する反応を予測する」ようなイメージに近い発想です。
② コードの動きを理解する:Code World Model(CWM)のインパクト
Code World Model(CWM)は、コード生成のためのLLMに「コード世界のシミュレーター」を組み合わせたような設計です。 具体的には、大規模なコードに加えて、Pythonコードの実行トレースや、 Docker環境でのエージェントによる開発作業軌跡を学習しています。 これにより、コードがどう動くかを内部で再現しながら、デバッグや修正案を考えられるように設計されています。
- コードの「見た目」だけでなく、「実行プロセス」を学んでいる
- 自分でテストケースを考え、自分の予測と実際の実行結果を比較する自己検証ループを持つ
- 研究用途のオープンウェイトモデルとして公開されており、今後の応用研究の土台になっている
マーケターにとって直接触れる機会は少ないかもしれませんが、 将来の「マーケティング・オペレーティングシステム」を裏側で支えるエンジンとして、 こうした世界モデル型のコーディングAIが組み込まれていく可能性があります。
③ LLM と世界モデルの「役割分担」が進みつつある
V-JEPA 2 や CWM のような研究は、「LLMだけで何でも行う」という発想から、 テキストはLLM、世界の状態推定は世界モデル、といった役割分担へシフトしていることを示しています。
- LLM: ユーザーとの対話、レポート生成、方針の説明など「言葉のインターフェース」を担当
- 世界モデル: 物理世界・行動ログ・コードなどの「状態と変化」の理解を担当
- 組み合わせ: マーケターが自然言語で問いかけると、世界モデル内部でシミュレーションし、その結果をLLMが分かりやすく説明する構造
世界モデルが入ると、AIが次のようなことをしやすくなります。
- 「このクリエイティブを出し続けたら、数週間後の指標はこんな推移になるかも」とシミュレーション
- 「この導線を変えたとき、どの行動パターンのユーザーが離脱しそうか」を仮想ユーザーで検証
- 「ある変更を本番に出す前に、仮想環境でABテスト的に試す」ようなワークフローの自動化
🛠️応用方法:世界モデルをマーケティングにどう生かすか
では、世界モデルの考え方を、デジタルマーケティングの現場でどのように活用できるでしょうか。 ここではすぐに全部を実装するというより、「世界モデル思考」でワークフローを設計し直す観点を整理します。
ユーザージャーニーの「シミュレーションボード」として使う
Web・アプリ・オフライン施策など、チャネル横断でユーザーの行動ログが蓄積されている場合、 それらを「世界の状態遷移」として扱い、世界モデル的に学習させる発想が考えられます。
- ページ遷移・スクロール・クリック・購買・解約などを「状態と行動」として記録
- その遷移パターンから、「この施策を打つと、どのようなルートを通るユーザーが増えそうか」を推定
- シミュレーション結果を、LLMが「4つの代表パターン」などに要約してくれると、意思決定しやすくなる
イメージとしては、ホワイトボードにこう描いていく感覚です。
- 🧍♀️ ユーザーの「状態」(初回来訪 / 比較検討 / 既存顧客…)
- ➡ 「行動」(閲覧・登録・解約・再来訪…)
- 🌀 施策を変えたときの「遷移確率」の変化
- 📊 その結果としての売上・LTV・チャーンの変化
この一連の動きを、世界モデルが内部で何度も試してくれるイメージです。
クリエイティブ・コンテンツの「行動影響」を学習する
V-JEPA 2 のような動画世界モデルは、物体や人の動きだけでなく、 「ある映像表現が続いたときに、視聴者がどのように行動を変えるか」といった応用にもつなげられる可能性があります。
- 動画広告の視聴ログと、その後のサイト行動やアプリ行動を世界モデルの観点で結びつける
- 「ここで商品をアップで見せると、比較ページへの遷移が増えやすい」といったパターンを抽出
- 今後は、AIがクリエイティブ案を生成するだけでなく、「行動への影響」を含めて提案してくる可能性もある
オペレーション自体を世界モデルで最適化する
Code World Model のようなアプローチは、マーケティングのオペレーション自体を自動化していくときの基盤になり得ます。 たとえば、次のような世界をイメージできます。
- 「毎週のレポート生成」「入札調整スクリプト」「タグ設定の変更」などを、エージェントが半自動で行う
- その際、世界モデルが「このスクリプトをこう変えると、システム全体にこういう影響が出そう」と予測
- 大きなリスクが見込まれる変更は、事前にアラートを出して人間にレビューを依頼
ここでは、世界モデルは「プロダクトの内部構造やコードの挙動を理解したパートナー」として機能し、 LLMが人間との会話や説明を担当するイメージです。
🚀導入方法:いきなり自前開発しないためのステップ
ここまで読むと、「世界モデル、面白そうだけど、自社でいきなり作るのは現実的ではない」と感じる方が多いと思います。 そこで、現実的な導入ステップを「世界モデル的な発想を取り入れる」というレベルから整理します。
ステップ1:自社の「世界」を定義する
まずは、AIに学習させたい「世界」の単位を言語化してみます。
- 対象: Webサイトか、アプリか、オフラインも含めた顧客関係か
- 状態: どんな状態変数を持っているか(閲覧状況、契約状況、行動頻度など)
- 行動: ユーザーがどんな行動を取れるか(閲覧・問い合わせ・購買・解約・シェアなど)
- 時間: どのくらいの期間を見たいか(数日単位なのか、半年以上を見たいのか)
ステップ2:ログを「世界モデル目線」で整理する
次に、既存の計測基盤やログを見直し、「状態と行動の遷移」として扱える形に整理していきます。
- ユーザー単位で時間順に並べられたイベントシーケンスを整える
- チャネルをまたいだときに、同じユーザーだと認識できるようなID設計を確認する
- 最低限の属性情報と組み合わせて、「どんな人が、どんな順序で動いているか」を可視化する
この段階では、世界モデルそのものを構築しなくても、 LLMに「このシーケンスをパターンごとに要約して」と依頼するだけでも、十分な学びがあります。
ステップ3:既存ツールや外部パートナーで PoC を行う
実際の世界モデル構築や物理シミュレーションを伴うようなユースケースは、 自前構築ではなく、プラットフォームやベンダーと連携して進めるケースが現実的です。
- 世界モデル系の研究を公開しているクラウドベンダーやAIベンダーと、PoCテーマを検討する
- まずは一つのユースケース(例:解約予兆シナリオのシミュレーション)に絞って試す
- LLMはフロントのインターフェースとして利用し、背後の世界モデルは専用基盤に任せる形を検討する
ステップ4:ガバナンスと「人間の役割」を明確にする
世界モデルを前提としたAIエージェントは、うまく設計すれば非常に頼りになる一方で、 誤った仮定のもとシミュレーションを進めてしまうリスクもあります。
- 「どのレベルまでをAIに任せ、どこから先は人間が必ずレビューするか」を明文化しておく
- モデルの前提条件や学習データの範囲を、マーケティングチームが理解できるようにドキュメント化する
- AIの提案をそのまま採用するのではなく、「仮説候補」として扱う文化をチーム内で共有する
🔭未来展望:LLMから「世界モデルOS」へ
世界モデル研究の進展を見ている研究者の中には、 数年スパンで「世界モデルを中核としたアーキテクチャ」が主流になると考える人もいます。 LLMは対話や文章生成のフロントとして残りつつ、その背後で世界モデルが環境理解や計画を担う構図です。
マーケティングの文脈では、次のような姿が想像できます。
- 世界モデルが、チャネル横断の顧客体験や広告エコシステムを「ひとつの世界」として学習
- マーケターは自然言語で、「この半年の目標」と「守るべき制約(予算・ブランド・法令など)」を指定
- エージェントが世界モデル内で複数のシナリオをシミュレーションし、現実世界では安全な範囲で実行
もちろん、すべてがすぐに実現するわけではありません。 ただ、Meta のような大規模プラットフォーマーが世界モデル路線を強く推進していることは、 「今のLLM前提の設計だけでなく、数年後の世界モデル前提のインフラも視野に入れておいた方がよい」 というシグナルでもあります。
今から準備しておきたいマーケターのスタンス
- 世界モデルの基本概念を、チーム内で共有できるレベルまで言語化しておく
- ログやイベント設計を、「状態遷移」として扱いやすい形に整備しておく
- ベンダー選定時に、「世界モデル的なアプローチ」にどう取り組んでいるかを質問してみる
🧾まとめ:世界モデルは「AI版・マーケティングシミュレーター」になり得る
Meta の世界モデル研究(V-JEPA 2 や Code World Model など)は、 「AIに世界を理解させ、行動の結果を事前に試す」という方向性を、具体的なモデルとして示しています。
- 世界モデルは、環境や行動の「状態遷移」を内部でシミュレーションする仕組み
- V-JEPA 2 は動画とロボットデータから物理世界の直感を学ぶ世界モデルの代表例
- Code World Model はコードの実行プロセスを学び、自己検証しながら開発を支援する研究モデル
- マーケティングでは、ユーザージャーニーや施策の組み合わせを「仮想世界」で試すという発想につながる
- いきなり自前開発するのではなく、「世界モデル思考」をログ設計やベンダー選定に取り入れることから始められる
LLMだけの世界から、「LLM × 世界モデル × エージェント」が前提となる世界へ。 いまのうちから構造の変化を押さえておくことで、 数年後に訪れるかもしれない「世界モデルOS時代」の波を、落ち着いて捉えやすくなります。
🙋FAQ:Metaの世界モデルとマーケティング担当者の関わり方
- 自社のユーザージャーニーを「状態」と「行動」に分解して、ホワイトボードや図で表現してみる
- 行動ログのシーケンスを、LLMに要約させて「代表的なパターン」を洗い出す
- ベンダーやパートナーとの会話で、「世界モデルやシミュレーション」にどう取り組んでいるかを質問する
- 施策の「試行回数」と「学習スピード」:シミュレーション環境内での検証が増えることで、現実世界での試行回数を抑えつつ学びを得られる可能性があります。
- チャーンやLTVなど、中長期の指標:短期的なコンバージョンだけでなく、時間軸を含めたシナリオを試せることで、長期的な影響を考慮しやすくなります。
- チームの意思決定スピード:AIが複数のシナリオを事前に検証してくれることで、人間が比較検討に使える情報が増えます。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。




-7-320x180.png)














-2025-06-19T165742.035-120x68.png)
-2025-11-06T150704.493-120x68.png)