オウンドメディア担当者が知っておくべき「LLMO視点」|SEOとのハイブリッド戦略の作り方
AI検索や生成AIが当たり前になり、「記事を量産してSEOだけを見る」やり方は限界が見えつつあります。本記事では、オウンドメディア担当者が今押さえておきたい「LLMO視点」と、既存のSEOと組み合わせたハイブリッド戦略の考え方を整理します。
SEOはこれまでどおり重要ですが、生成AIやAI検索がまとめた回答の中で、オウンドメディアのコンテンツがどう扱われるかという視点が欠かせなくなっています。
イントロダクション
オウンドメディアのKPIといえば、「セッション数」「検索順位」「オーガニック流入」など、いわゆるSEO起点の指標が中心になりがちです。編集会議でも、「このキーワードで上位を狙おう」「検索ボリュームが多いテーマを増やそう」といった会話が多いのではないでしょうか。
一方で、ChatGPTやGemini、Perplexityなどの生成AIを日常的に使う人が増え、検索エンジンもAI概要やAIモードなどを通じて、「キーワードからリンク一覧」ではなく「質問から答え」に近い体験を提供し始めています。
この変化は、オウンドメディアの役割にも影響します。ユーザーはこれまで以上に、AIが整理した要約や比較コメントを通じて情報に触れるようになります。そのとき、AIが参照する情報源としてオウンドメディアは選ばれているか、という問いが生まれます。
そこで登場するのが、LLMO(Large Language Model Optimization)という視点です。LLMOは、生成AIやAI検索に自社コンテンツを正しく理解・引用してもらうための考え方であり、SEOと対立するものではなく、むしろオウンドメディアの価値を整理し直すヒントになります。
「AIが組み立てた答えの中で、オウンドメディアがどう見えるか?」をセットで考えるのが、LLMO視点の第一歩です。
概要:LLMOとSEOの違い・共通点
LLMOは「Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)」の略で、生成AIやAI検索が回答を作る際に、自社コンテンツを正しく理解し、引用しやすくするための最適化を指します。SEOと似た言葉ですが、対象となる「エンジン」が異なります。
- 検索エンジン(主にGoogle)の結果ページにどう表示されるか
- 特定キーワードでの順位やクリック率、セッション数などが主な評価軸
- タイトルタグ、見出し、内部リンク構造、ページスピードなどが重要
- 生成AIやAI検索が作成する回答文の中で、どう取り上げられるか
- AIが引用する出典として、どのページ・ドメインが選ばれるか
- 情報の構造化、エンティティ(人物・企業・サービス)の一貫した表現が重要
オウンドメディアにとってのハイブリッド戦略とは
オウンドメディアの現場では、SEOとLLMOを対立軸として捉える必要はありません。むしろ、次のように役割を整理するとイメージしやすくなります。
- SEO: 検索結果からの直接流入を育てる(入口を増やす)
- LLMO: AIの回答を通じて「見つけられ方・語られ方」を整える
- ハイブリッド: 両方を前提に、サイト全体の情報設計・コンテンツ戦略を組み立てる
- ユーザーの「検索行動」と「質問行動」の両方を想定する
- オウンドメディア・レビューサイト・SNSなど、複数のタッチポイントでの一貫性を保つ
- AIが参照しやすい構造(Q&A・箇条書き・定義文)を増やす
利点:オウンドメディアがLLMO視点を取り入れる価値
「SEOだけでも手一杯なのに、さらにLLMOまで…」と感じるかもしれません。ただし、LLMO視点を取り入れることは、新しい施策を増やすだけでなく、既存のオウンドメディア運営を見直すきっかけにもなります。
AI検索・AIチャット経由の接点を見逃しにくくなる
生成AIやAI検索は、「比較したい」「判断軸を整理したい」といった相談ベースのニーズとの相性が良いと言われます。GEO(Generative Engine Optimization)の議論でも、AIの回答でどう取り上げられるかが重要なテーマとして語られています。
- 従来のSEOでは拾いきれなかった「長めの質問」「口語的な悩み」にも対応しやすくなる
- AIが作る比較コメントの中で、自社のオウンドメディアが根拠の一つとして紹介される可能性が高まる
- 検討初期の段階で、ブランドが自然に候補に入るきっかけを増やせる
オウンドメディアの情報を「社内外のナレッジ」として再活用しやすくなる
LLMO対応では、Q&Aやチェックリスト、ステップ解説など、構造化されたコンテンツを意識することが多くなります。これは、営業資料やサポートナレッジ、ウェビナーの台本などに転用しやすい形でもあります。
- 記事の一部をそのまま社内FAQや提案資料に流用できる
- 社内AIアシスタントの学習データとしても使いやすくなる
- 「オウンドメディア=ナレッジのハブ」という位置づけが強まりやすい
ブランドの専門性・一貫性を整理するきっかけになる
AI検索に関する研究や実務の議論では、「信頼できる情報源」「一貫性のあるエンティティ」が重視される傾向が指摘されています。
- 企業名・サービス名・略語などの表記ゆれを減らす必要が出てくる
- ブランドとして「何を専門領域とするのか」を言語化しやすくなる
- 著者情報・実績・事例など、信頼性を示す要素の整理につながる
「SEOだけの評価軸」から抜け出しやすくなる
オウンドメディアの報告資料は、どうしてもセッションや順位、CV数など、SEO寄りの指標に偏りがちです。そこにLLMO視点を加えることで、次のような観点も話しやすくなります。
- AIの回答の中で、どのような文脈とセットでブランドが紹介されているか
- 比較・選び方の記事が、AIにとっても引用しやすい中立的なコンテンツになっているか
- 「指名検索」だけでなく、「テーマ×ブランド」で語られる状態を作れているか
数字だけでは見えにくい「語られ方」「位置づけ」の変化を確認しやすくなるのも、LLMO視点のメリットです。
応用方法:オウンドメディアでの具体的なLLMO活用イメージ
ここからは、オウンドメディアの企画・編集・改善のプロセスに、LLMO視点をどう組み込むかを具体的にイメージしていきます。
記事単体ではなく「質問の束」として設計する
生成AIやAI検索から見たとき、1本の記事は「いくつかの質問に対する答えの集合」として扱われます。そのため、記事を企画するときに、次のようなメモを用意しておくとLLMOと相性が良くなります。
- このテーマでユーザーが投げそうな質問を5〜10個書き出す
- その質問に対する「1〜2文の結論」をあらかじめ用意する
- 本文では、その結論を補う背景・具体例・注意点を丁寧に説明する
エンティティページでブランドの「公式な説明」を整える
LLMOやGEOの議論では、企業やサービスなどの「エンティティ」が重要なキーワードとして扱われます。オウンドメディアでは、ブランド・サービス単位で情報を整理したエンティティページを用意しておくと、AIにも人にも親切です。
- ブランドの概要・提供価値・特徴を1ページにまとめる
- よくある質問や比較されやすいサービスとの違いをQ&A形式で掲載する
- 関連するブログ記事・事例・ホワイトペーパーへのリンクを整理する
「比較・選び方」コンテンツをニュートラルに設計する
AIは、あまりにも広告色の強い文章よりも、比較的ニュートラルで整理された情報を好んで引用する傾向があると指摘されることがあります。オウンドメディアの比較コンテンツでは、次のような点に気を配るとLLMOとも相性が良くなります。
- 自社・他社の双方のメリット/注意点を整理して記載する
- 「どんな条件の人には合いやすいか/合いにくいか」を明示する
- 結論を押し付けるよりも、判断軸やチェックポイントを提示する
社内AIと連携した「記事テーマ発掘」のサイクルをつくる
LLMO視点は、コンテンツの発掘にも活用できます。例えば、次のようなサイクルが考えられます。
- 営業やサポートの問い合わせ内容を社内AIで分類し、「よくある質問」を一覧化する
- その中から、オウンドメディアで記事化すべきテーマを選び、優先順位をつける
- 公開した記事を、社内AIの回答にも利用できるようリンクや要約を連携する
「実際の質問」ベースで記事テーマを決めることで、LLMOとも親和性の高いコンテンツ群が自然と増えていきます。
導入方法:LLMO視点をオウンドメディア運営に組み込むステップ
ここでは、「明日から何を変えればよいか」をイメージしやすいように、オウンドメディア担当者向けの導入ステップを整理します。すべてを一気に進める必要はなく、既存のSEO施策に少しずつLLMO視点を足していくイメージで問題ありません。
現状把握:AIから見た「自社の姿」をラフに確認する
まずは、生成AIやAI検索で次のような質問を投げてみるところから始められます。
- 「◯◯社とは?」(自社名)
- 「◯◯社の◯◯サービスについて教えて」
- 「◯◯業界でおすすめのツール/サービス」
そこで表示される説明文や引用サイトを、スクリーンショットやメモとして残しておくと、後からの比較に役立ちます。
重要ページの洗い出し:最初に整えるべき「コア」コンテンツを決める
AIから見た状態を軽く把握したら、次はオウンドメディア側で「まず整えるべきページ」を選びます。例えば、以下のようなページ群が候補になりやすいです。
- 会社概要・サービス概要など、ブランドの基本情報を説明するページ
- 代表的な製品・サービスごとの詳細ページ
- 検索・AI経由でよく読まれている基礎解説記事
- 比較・選び方・チェックリストなどのナビゲーション系コンテンツ
コンテンツの型を決める:LLMO対応の「テンプレート」を用意する
チームで運営しているオウンドメディアの場合、コンテンツの型を共有しておくことが、LLMO視点を浸透させる近道です。例えば、基礎解説記事であれば次のような構成テンプレートを用意できます。
- 冒頭:一言サマリー+誰向けの記事か
- 用語の定義:短い定義文+かんたんな例
- メリット・注意点:箇条書きで整理
- 手順・進め方:ステップ形式で紹介
- よくある質問:Q&A形式で3〜5個
構造化・技術面の基本を押さえる
LLMO視点のコンテンツ設計と並行して、従来のSEOでも推奨されてきた構造化データや技術面の整備を行うと、AIにとっても理解しやすいサイトになります。
- FAQページにはFAQ構造化データを検討する
- OrganizationやProductなど、基本的なマークアップを必要に応じて実装する
- タイトル・見出し構造・パンくずリストなど、基本的なSEOの土台を整える
評価・共有:シンプルな「LLMOメモ」をレポートに追加する
SEOレポートに、次のようなシンプルなLLMOメモを1〜2ページ追加するだけでも、社内での理解が進みやすくなります。
- AIで自社名を検索したときの説明文のスクリーンショット
- AI回答で出典として紹介されている自社ページの一覧
- 今後整えたいページと、想定する「質問」のセット
数値にしにくい部分もありますが、「どう語られているか」の変化を定期的に観察することで、施策の方向性を調整しやすくなります。
未来展望:AI検索・AIエージェント時代のオウンドメディア
生成AIやAI検索はまだ発展途上ですが、GEOやAI SEOに関する議論やレポートは増えつつあります。そこでは、「AIがどの情報源を好んで参照するか」「どんな特徴のコンテンツが引用されやすいか」といった視点が整理されつつあります。
AIエージェントが「誰の情報をもとに動くか」という問い
近い将来、スケジュール調整や情報収集、資料作成まで含めてサポートするAIエージェントが広く使われると考えられています。そのとき、エージェントが意思決定の材料として参照する情報源の中に、オウンドメディアがどの程度含まれているかは、ビジネスにとって無視しにくいポイントになります。
- 「◯◯業界の主要なプレーヤーと特徴をまとめて」と依頼したとき、どのブランドがリストアップされるか
- 「◯◯の比較表を作成して」と指示したときに、オウンドメディアの情報が引用されるか
- AIエージェントが「おすすめの資料」として提示するPDFや記事の中に、自社コンテンツが含まれているか
「SEOの終わり」ではなく、「役割の分担」が細かくなる
AI検索の台頭とともに、「SEOは終わるのか?」という問いがしばしば取り上げられます。しかし、多くの専門家や実務者は、「良いSEOの土台が、GEOやLLMOにも役立つ」という見方を示しています。
オウンドメディアの文脈では、次のように整理すると前向きに捉えやすくなります。
- SEO:検索エンジンの結果ページという「入口」を整える
- LLMO/GEO:AIが生成する回答という「別の入口」での見え方を整える
- コンテンツマーケティング全体:両方を踏まえて、ユーザーの意思決定を支援するストーリーを設計する
オウンドメディア担当者に求められるマインドセット
最後に、AI時代のオウンドメディア担当者に求められるマインドセットを、ラフなメモとしてまとめます。
- 「どのキーワードで上位を狙うか」だけでなく、「どんな質問にどう答えるメディアでありたいか」を考える
- 記事単体ではなく、「サイト全体でどんな物語を語るか」という視点を持つ
- AIツールも活用しながら、企画・執筆・振り返りのサイクルを軽やかに回す
- SEO・LLMO・広告・SNSなど、チャネル横断でメッセージの一貫性を意識する
オウンドメディアは、「AIにとっても」「人にとっても」頼りになる情報源を目指せるポジションにあります。そのポテンシャルを活かすためのレンズの一つが、LLMO視点だと考えるとイメージしやすいはずです。
まとめ:オウンドメディアを「AIにも伝わるメディア」に育てる
- LLMOは、生成AIやAI検索が回答を作るときに自社コンテンツを理解・引用しやすくするための考え方
- SEOとLLMOは対立関係ではなく、「検索結果」と「AIの回答」という異なる入口を担当する関係
- オウンドメディアでは、質問ベースの構成・エンティティページ・比較コンテンツのニュートラルさが特に重要
- 導入時は、現状把握 → 重要ページの洗い出し → コンテンツの型づくり → 構造化・技術面の整備 → シンプルな評価メモ、という流れが進めやすい
- AIエージェント時代を見据え、「誰のどんな意思決定を助けるメディアにしたいか」を起点に、SEOとLLMOのハイブリッド戦略を組み立てることが有効
オウンドメディアは、これからも企業とユーザーをつなぐ重要な接点であり続けます。環境の変化にあわせて、SEOにLLMOというレンズを重ねることで、「検索にもAIにも強いメディア」へと育てていくことができます。日々の企画や記事レビューの中に、少しずつLLMO視点を取り入れていくところから、ぜひはじめてみてください。
FAQ:オウンドメディア × LLMO視点に関するよくある質問
SEOの優先度を下げる必要はありません。むしろ、良質なコンテンツ設計や構造化、ユーザー体験の改善など、SEOの基本はLLMOとも共通する土台になります。実務的には、既存のSEO施策をベースにしながら、「質問ベースの構成」「エンティティページ」「FAQの充実」など、LLMOと相性の良い改善を少しずつ追加していくイメージがおすすめです。
あります。テーマが絞られたオウンドメディアは、専門性や一貫性を示しやすく、AIから見ても理解しやすい情報源になりやすいからです。まずは、自社が得意とするテーマの「基礎解説」や「よくある質問」に絞って、Q&A形式の記事やエンティティページを整えるところから始めると、負荷を抑えつつ取り組めます。
現時点では、SEOのように明確な共通指標が整っているわけではありません。そのため、「厳密な数値管理」よりも、「変化の傾向を観察する」スタンスが現実的です。例えば、AIで自社名を検索したときの説明文の変化や、AI回答で出典として表示されるページの種類、AI検索経由と考えられる問い合わせ内容の変化などを、定期的にメモとして残しておくと方針の見直しに役立ちます。
まずは編集・ライティングの範囲でできることから始めるのがおすすめです。具体的には、「見出しを質問風にする」「各セクションの冒頭に一言サマリーを追加する」「記事末尾に簡単なFAQを設ける」といった改善は、開発リソースがなくても実施できます。そのうえで、必要に応じてFAQ構造化データやエンティティ関連のマークアップなど、技術的な対応をピンポイントで検討すると進めやすくなります。
LLMOやGEOの議論では、オウンドメディアだけでなく、外部の評価やレビュー、メディア掲載などもAIが参考にする情報源として注目されています。オウンドメディアは「公式な説明」「深い解説」を担いながら、SNSや外部メディアでの発信・評価とも組み合わせて、全体として一貫したメッセージを届けることが大切です。その意味で、オウンドメディアはハブとしての役割を持ちつつ、他チャネルとの連携を意識した設計が求められます。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。





-7-320x180.png)












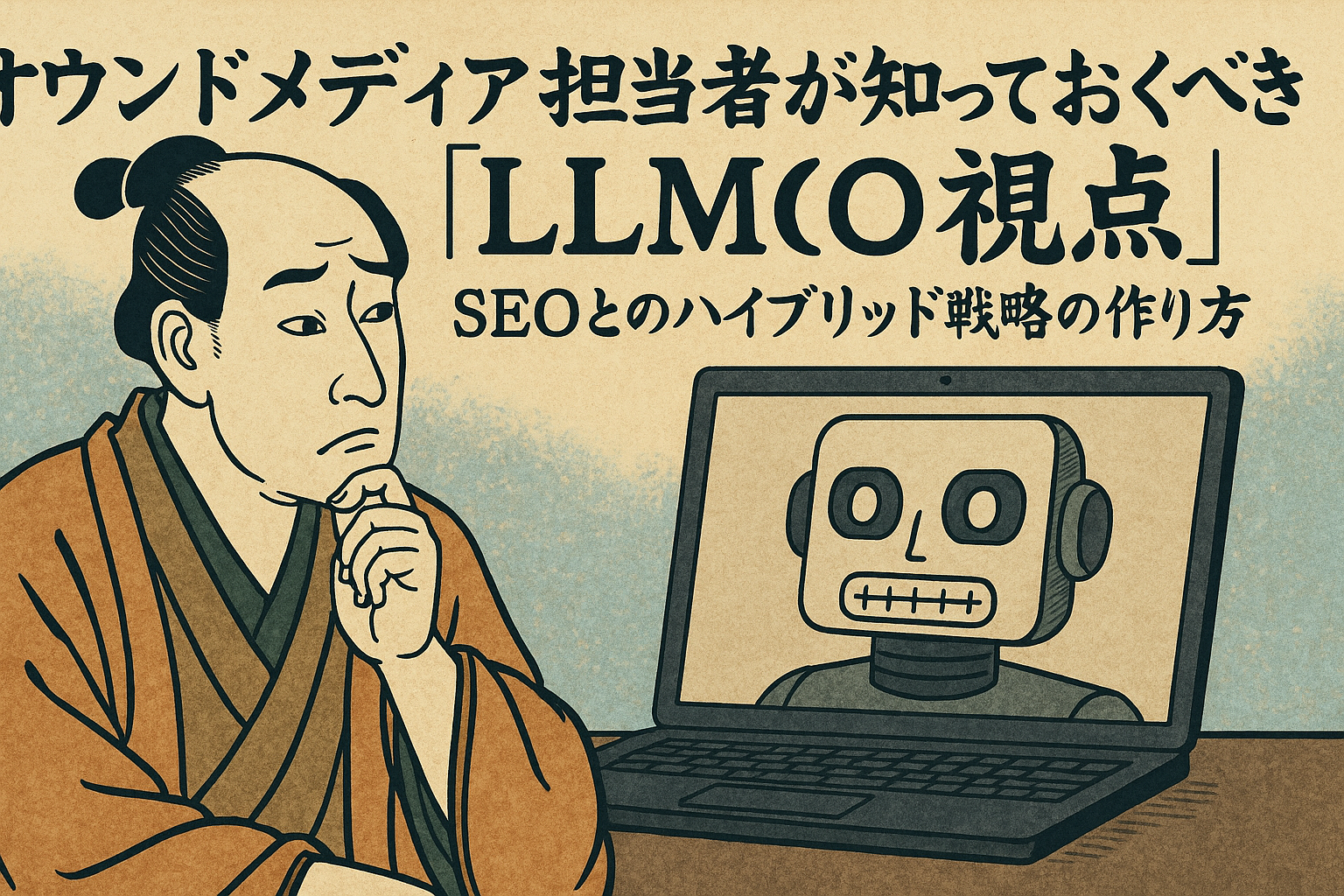
-43-120x68.png)
-76-120x68.png)


