序論:AIブームの裏で語られる新たな視点 – 「AI帝国」の台頭
日本のビジネスシーンは今、生成AIの話題で持ちきりだ。デジタルマーケティング業界においても、その熱狂は日増しに高まっている。「営業支援ツール【GoQMieruca】V3移行で利便性向上」「ウェブサイトから商談が自動で生まれる、AIエージェント」といった新サービスのニュースが連日のようにメディアを飾り 、多くの企業が「SEO×PR連携」や「LLMO(大規模言語モデル最適化)対策」といった新たな施策に乗り出している 。『MarkeZine』や『Web担当者フォーラム』といった主要メディアも、AI活用の成功事例や最新ツールの比較記事で溢れており、いかにしてAIを自社の業務効率化や顧客体験向上に結びつけるかが、マーケターにとって最大の関心事となっている。
しかし、この実用主義的なAI活用の議論が白熱する一方で、テクノロジーの中心地であるシリコンバレーからは、全く異なる、より根源的な問いが投げかけられている。米国の有力テックメディア『TechCrunch』が報じた、著名なジャーナリスト、カレン・ハオ氏による「AIの帝国(Empire of AI)」という鋭い視点だ 。この記事は、OpenAIの急成長を単なるビジネスサクセスストーリーとしてではなく、「イデオロギー的な物語」として捉え直すことを提言している 。ハオ氏が指摘するのは、AI開発の最前線が「AGI(汎用人工知能)の伝道者たち」によって牽引され、その「信念」が巨大なエコシステムを形成し、その過程で看過できない「代償」が支払われているという現実である。
この視点は、日本国内で主流となっている「AIをいかに使うか」というツール中心の議論とは一線を画す。それは、「我々が使おうとしているAIとは、そもそも何なのか?」という、その本質と構造を問うものだ。日本のマーケターが日々接しているAIツールやサービスは、この「帝国」が生み出した産物である可能性が高い。だとすれば、その背景にある思想や力学を理解せずして、真に戦略的なAI活用はあり得ないのではないか。本稿では、TechCrunchが提起した「AI帝国」の概念を深掘りし、そのイデオロギー構造、中核をなすOpenAIの実態、そしてそれがもたらすリスクを分析する。最終的には、この新たな視点が日本のデジタルマーケティング担当者や経営者にとって、いかなる戦略的示唆を持つのかを考察していく。
「AGIへの信仰」が巨大資本を動かす – AI帝国のイデオロギー構造
カレン・ハオ氏が提唱する「AI帝国」論の核心は、その中心に強力な「イデオロギー」が存在するという指摘にある。「あらゆる帝国の中心には、システムを前進させ、その拡大を正当化するイデオロギー、すなわち信念体系が存在する」と彼女は述べる 。歴史上の帝国が特定の宗教や思想を掲げて領土を拡大したように、現代のAI開発競争もまた、一つの強烈な信念によって駆動されているというのだ。
その信念こそが、「AGI(汎用人工知能)の実現」である。AGIとは、人間と同等かそれ以上の知性を持ち、あらゆる知的作業をこなすことができるAIを指す。現在のAI開発をリードする企業群にとって、AGIの追求は単なる技術目標ではない。それは「人類全体に利益をもたらす」という崇高な使命を帯びた、一種の信仰、あるいは「AGIカルト」とでも言うべきものに変貌している。
このAGIという壮大なビジョンは、極めて強力な機能を持つ。まず、それは数十億ドル規模の資金調達競争を煽り、正当化する 。通常であれば独占禁止法などの観点から問題視されかねないほどの巨大な計算資源(コンピュート)とデータへの投資も、「AGIという人類の夢を実現するためには不可欠なコスト」として合理化される 。実際に、最先端のAIモデルを学習させるためには、「数万個のGPUを搭載した巨大なAIデータセンター」のような、天文学的な規模のインフラが必要となる 。AGIという目標がなければ、これほどの資源集中を社会的に容認させることは難しいだろう。
このようにして、AGIへの信仰は、「使命と利益の境界線を曖昧にする」効果をもたらす 。企業の営利活動が、人類を救済するための神聖な探求であるかのように語られる。このイデオロギーを熱心に説くリーダーたちは「AGIの伝道者(evangelists)」と呼ばれ 、彼らの言葉は投資家やエンジニア、そして社会全体を巻き込み、巨大なエコシステムを形成していく。つまり、AGIという概念は、技術開発の指針であると同時に、資本を集め、競争を正当化し、社会的な批判をかわすための、極めて洗練された「物語装置」として機能しているのである。これが、ハオ氏の言う「AI帝国」のイデオロギー的な構造だ。
ケーススタディ:OpenAI – 「人類の利益」と「企業利益」の狭間で揺れる寵児
この「AI帝国」のイデオロギーと内部矛盾を最も象徴的に体現しているのが、ChatGPTの開発元であるOpenAIだ。同社の物語は、ハオ氏の論考を裏付ける格好のケーススタディとなる。
OpenAIは元々、「AIの安全な開発」を最優先事項とする非営利団体として設立された。その根底には、強力なAIが人類にもたらす潜在的なリスクへの深い懸念があった。しかし、ChatGPTの爆発的な成功を機に、社内の力学は劇的に変化する。当初の「我々は慎重でなければならない」という安全志向の思想は、次第に「AGIの恩恵を全人類に行き渡らせるため、可能な限り迅速にこの技術を展開する必要がある」という、展開を急ぐ思想へと取って代わられていった。
このイデオロギーの対立が表面化したのが、2023年に世界を揺るがした取締役会によるサム・アルトマンCEOの解任劇である。このクーデターの背景には、OpenAIを「精神的には依然として非営利団体」と捉え、安全性や倫理を商業的成功よりも優先すべきだと考える旧来の取締役会メンバーと、アルトマン氏が率いる急進的な商業化路線との深刻な亀裂があった 。結果的にアルトマン氏は復帰を果たし、商業化路線が勝利を収めたが、この一件は、設立当初の崇高な理念が、巨大な商業的成功の波にいかに脆く、飲み込まれてしまうかを白日の下に晒した。
この変節の過程で重要な役割を果たしたのが、アルトマン氏自身のリーダーシップスタイルだ。彼は、自らのビジョンに賛同する人々からは「驚異的な資産」と見なされる一方で、そのビジョンに反対する人々からは「巧みな人心掌握術を駆使するマニピュレーター」と評される、毀誉褒貶の激しい人物である 。彼は「人間の心理を非常によく理解」しており、卓越した才能を持つ人材を惹きつける能力に長けている 。このカリスマ性が、OpenAIを非営利の研究機関から、世界で最も注目されるテクノロジー企業へと変貌させる原動力となった。アルトマン氏の解任騒動の最中、社内で「アルトマンが大統領選に出馬するのでは?」という冗談が飛び交ったというエピソードは 、彼の存在がいかに会社の方向性を決定づける象徴的なものであったかを物語っている。
OpenAIの取締役会議長自身が、現在のAI業界がドットコム時代のような「バブル」にあると認めつつも、その先にある経済変革を確信していると語っているように 、この熱狂は巨大な期待と投機に支えられている。OpenAIの事例が示すのは、ひとたびテクノロジーが大きな商業的価値を持つと、それを管理するために設計された倫理的なガバナンス構造そのものが、利益追求の圧力によって形骸化してしまうという厳しい現実だ。「人類の利益」という当初の使命は、結果的に「帝国」の拡大を正当化するためのスローガンへと変質してしまったのである。
信念の代償:AI帝国が消費する資源と見過ごされるリスク
AGIという壮大な「信念」は、帝国を築き上げる原動力となる一方で、社会や環境に対して決して小さくない「代償」を要求する。このコストは、帝国の輝かしい成功の影に隠れ、見過ごされがちだ。
最も物理的で明白なコストは、環境への負荷である。AI帝国を支えるのは、膨大な計算能力であり、それは「数万基のGPUを搭載した巨大なAIデータセンター」によって供給される 。これらの施設は凄まじい量の電力を消費し、そのエネルギー需要の増大に各国が悲鳴を上げ始めているのが現状だ 。AGIの実現という目標のために、地球規模でのエネルギー消費と二酸化炭素排出量が加速している。この環境コストは、AI企業の貸借対照表には計上されないが、社会全体が負担すべき負債として着実に積み上がっている。
次に、社会的なコストが挙げられる。最先端のAIモデルは、インターネットから収集された膨大なデータを学習して構築されるが、そのデータの出所は不透明な場合が多い。著作権で保護されたコンテンツや個人情報が含まれている可能性も指摘されており、倫理的・法的な問題をはらんでいる。さらに、AIは我々の社会における「信頼」のあり方を根底から揺るがし始めており、「 profound Trust Revolution(深刻な信頼革命)」を引き起こしているとの見方もある 。我々は、その内部動作を完全には理解できない強力なツールに対し、「いかにして安全で、有益で、我々の価値観と真に一致していることを保証するのか」という、未曾有の課題に直面しているのだ。
最後に、市場における戦略的なコスト、すなわち権力集中のリスクがある。AI開発が一部の巨大企業に独占されることで、健全な競争環境が阻害される恐れがある。現在、オープンソースモデルの台頭により、巨大AI企業が単なる「低マージンのバックエンド」供給者に追いやられる可能性も指摘されているが 、依然として計算資源や最高レベルの人材は一部のプレイヤーに集中している。特定の企業のプラットフォームに依存することは、将来的な価格引き上げやサービス変更のリスクを抱え込む「ベンダーロックイン」につながり、企業の戦略的自由度を著しく低下させる可能性がある。
これらのコストはすべて、AGIという「信念」を追求する過程で生じる外部不経済である。利益はAI帝国の中枢に集中し、その過程で生じる環境的・社会的な負債は社会全体に転嫁される。カレン・ハオ氏が問う「信念の代償(the cost of belief)」とは、信者である企業自身が支払うものではなく、帝国に属さない我々全員が支払わされているコストなのである。
帝国への対抗軸:カレン・ハオが描く「人間中心の分散型AI」という未来
カレン・ハオ氏の分析は、単なる批判に留まらない。彼女は「AI帝国」という現状への対抗軸として、全く異なる未来の可能性を提示する。それは、中央集権的な帝国モデルから脱却し、「データを搾取し、人間と天然資源を食い物にする帝国から、より分散化され、人間中心の(human-centric)権力配分へとAIを方向転換させる」というビジョンだ。
この代替案は、AIの権力構造そのものを問い直すものだ。現在の帝国モデルが、少数の巨大企業にデータと計算能力、そしてルールメイキングの権限を集中させるのに対し、分散型モデルは、その権力をより多くの個人や組織に再分配することを目指す。この思想は、近年注目を集めるオープンソースの大規模言語モデルの動向とも共鳴する。オープンソースモデルの進化は、巨大AI企業をコモディティ化したバックエンドインフラの提供者に変え、イノベーションの主導権をより広範な開発者コミュニティにもたらす可能性を秘めている。
「AI帝国」モデルと「人間中心の分散型」モデルの違いを明確にするため、以下の表にその特徴をまとめる。
この比較から浮かび上がるのは、単なる技術的なアプローチの違いではなく、AIと社会の関係性に関する根本的な哲学の違いである。帝国モデルがAIを自律的に進化する知能として捉え、その最大化を目指すのに対し、人間中心モデルはAIをあくまで人間の能力を拡張するためのツールとして位置づけ、そのコントロールを人間の手に留めようとする。この対立軸を理解することは、これから企業がAI戦略を立てる上で、どの未来像に自らを位置づけるのかを決定する、極めて重要な羅針盤となるだろう。
日本のデジタルマーケティングへの示唆:我々はいかにAIと向き合うべきか
カレン・ハオ氏が提示した「AI帝国」という視点は、日本のデジタルマーケターや経営者に何を問いかけるのか。それは、日々のAI活用をより高い解像度で捉え直し、戦略的な意思決定を行うための新たなフレームワークを提供する。
現在、日本国内のマーケティングメディアで語られるAIの議論は、『MarkeZine』や『ITmedia Marketing』に見られるように、成功事例の共有、ツールの機能比較、そして投資対効果(ROI)の算出が中心だ 。これらは実務において不可欠な情報である。しかし、「AI帝国」の視座に立てば、これまでのベンダー選定基準に新たな一層、すなわち「思想的なデューデリジェンス」を加える必要性が浮かび上がってくる。
例えば、サイバーエージェントが開発した広告効果予測AIツールのように 、特定のAI技術を自社のコア業務に組み込む際、我々は単にその性能や価格を評価するだけでは不十分となる。そのツールがどの「帝国」のエコシステムに属しているのか、その基盤となるモデルはどのようなデータで学習され、いかなる倫理観に基づいているのかを問わなければならない。なぜなら、特定のAIベンダーのAPIを深く組み込むことは、単なるツールライセンスの契約ではなく、その帝国が描く技術ロードマップ、倫理観、そしてビジネスモデルに自社の未来を賭けるという、長期的な「エコシステムへの合流」を意味するからだ。
この選択は、一度行うと後戻りが難しい。もしベンダーがAPIの仕様を大幅に変更したり、価格を釣り上げたり、あるいは自社のブランド価値と相容れない倫理的な判断を下した場合、そこから脱却するコストは計り知れない。これはもはや、マーケティング部門やIT部門だけの問題ではなく、企業のリスクマネジメントや長期的自律性に関わる、経営レベルの戦略課題である。
奇しくも、このような権力集中への懸念は、日本国内でも「国産AI」の開発推進 や、国家がデータ主権を確保する「ソブリンAI」という概念の登場 といった形で顕在化し始めている。これらは、特定の海外「帝国」への過度な依存がもたらす戦略的リスクを、国家レベルで認識し始めたことの証左と言えるだろう。
AI活用コンサルタントが「まずは関心のあることから試してみるのが一番」とアドバイスするように 、AIに触れ、試行錯誤することの重要性は変わらない。しかし、これからはその一歩先に進み、我々が試しているそのツールが、どのような未来像の一部なのかを自問する必要がある。ツールの向こう側にある「帝国」の姿を意識すること。それが、これからのデジタルマーケターに求められる新たなリテラシーなのである。
結論:ツールとしてのAIから、パートナーとしてのAIへ
TechCrunchが報じ、カレン・ハオ氏が深く掘り下げた「AI帝国」という概念は、我々がこれまで慣れ親しんできたAIに対する見方を根底から覆す力を持つ。それは、AIを単なる便利な「ツール」としてではなく、特定の思想と目的を持って構築された巨大な「エコシステム」として捉え直すことを促す。AGIという壮大なビジョンが、いかにして巨大資本を動かし、OpenAIのような企業を成功へと導き、そしてその裏でどのような代償が支払われているのか。この一連の構造を理解することは、もはや技術者や倫理学者だけの課題ではない。AIを事業の根幹に据えようとするすべてのビジネスパーソンにとって、不可欠な戦略的視点である。
ハオ氏が最終的に示すのは、悲観論ではなく、我々自身の選択の重要性だ。彼女は「AIの未来に関して、私たちには主体性(agency)がある」と結論づける 。中央集権的な帝国モデルが唯一の道ではない。より分散化され、人間中心の価値観に基づいたAIのあり方を模索し、選択することは可能なのである。
これは、「機械 対 人間」という単純な二項対立の物語ではない。むしろ、「機械 と 人間が共に世界を再創造していく」という未来像そのものだ 。ただし、そこには重要な問いが伴う。我々は、どの機械と、そしてどの未来像と、パートナーシップを結ぶのか?
マーケターとして、経営者として、我々は日々、テクノロジーに関する無数の選択を行っている。どのツールを導入し、どのプラットフォームに投資し、どのデータを利用するのか。これからは、その一つひとつの選択が、我々が望むAI社会の未来像に対する一票となる。AIがビジネスと社会に深く浸透していく中で、我々の思考もまた進化しなければならない。単にAIを「使う」存在から、その価値観や方向性を見極め、自社と社会にとって最良の未来を共創できる相手として、AIを主体的に「選ぶ」存在へ。その意識の転換こそが、「AI帝国」の時代を生き抜くための、最も重要な鍵となるだろう。
参考サイト
TechCrunch「Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief」

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。




-2025-09-05T151236.591-320x180.png)








-7-320x180.png)




-2025-09-16T185512.443.png)
-2025-06-03T191433.569-120x68.png)
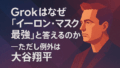
-2025-09-16T171404.129-120x68.png)
-2025-09-17T151651.224-120x68.png)