従来のマーケティング測定における根本的な欠陥
はじめに:加算的ダッシュボードの幻想
現代のマーケティングリーダーは、日々、Google AdsやMeta Adsといったプラットフォームが提供するダッシュボードと向き合っている。そこには、クリック数、コンバージョン数、獲得単価といった指標が整然と並び、一見するとマーケティング活動の成果を正確に示しているかのように見える。しかし、この見かけの明瞭さには、重大な落とし穴が潜んでいる。これらのツールは、その構造上、各チャネルの成果を個別のものとして扱い、それらを単純に足し合わせた「加算的」な世界観を提示するからである。
このレポートの中心的な論点は、マーケティングの真の成果は足し算(加算)ではなく、掛け算(乗算)や相乗効果によって生まれるという事実である 。この根本的な認識の違いを理解することが、競争優位性を築く第一歩となる。この概念を直感的に理解するために、身近な例え話を考えてみよう。「ミルクとオレオクッキー」の組み合わせである。冷たいミルクもオレオクッキーも、それぞれ単体で十分に楽しめる。しかし、これらを組み合わせることで、単なる個々の満足度の合計をはるかに超える、全く新しい次元の体験が生まれる。マーケティングにおける相乗効果もこれと同様で、戦略的に統合された施策は、個々の活動の総和では決して到達できないレベルにまで成果を増幅させるのである。
しかし、多くの組織では、各チャネルの担当者がそれぞれのKPIを追い、その単純な合計値を全体の成果として報告する慣行が根強く残っている。この「加算的」な思考様式は、マーケティング活動が本来持つポテンシャルを著しく制限するだけでなく、最も価値のある成長機会を見過ごす原因となっている。本レポートでは、この加算的な幻想から脱却し、乗算的かつ相乗的な成果を生み出すための理論的背景、測定モデル、そして戦略的フレームワークを詳述する。
マーケティングインパクトの再定義:新たな分類体系
マーケティング活動がもたらす効果を正しく理解するためには、まずその種類を明確に分類する必要がある。効果は単純なものではなく、その性質に応じて「加算的」「乗算的」「相乗的」の3つに大別できる。
加算的効果(1+1=2)
これは最も単純で、多くのマーケティングレポートの根底にある考え方である。各チャネルやキャンペーンの成果は互いに独立しており、全体の成果は個々の成果の単純な合計に等しいと仮定する。例えば、キャンペーンAが100件のリードを、キャンペーンBが200件のリードを獲得した場合、合計の成果は300件のリードとなる 。このモデルは、ラストクリックアトリビューションのように、特定のタッチポイントのみに成果を帰属させる測定方法の基礎となっている。各施策が互いに影響を与えないという前提に立つため、本質的にサイロ化されたチャネル管理を助長する。
乗算的効果(1×1.5=1.5)
これは、あるマーケティング活動が他の活動の効果を増幅させる、より高度な概念である。全体の効果は、各要因の単純な和ではなく、積で表される。例えば、ブランドキャンペーンによって製品認知度が2倍になり(要因1)、その結果としてダイレクトレスポンス広告のコンバージョン率が1.5倍に向上した(要因2)とする。この場合、売上への複合的なインパクトは 倍となり、単純な足し算では説明できない成果が生まれる 。ここでは、チャネル間の相互依存性が認識されており、加算的モデルよりも現実に近い。
相乗効果(1+1=3)
これは最も洗練され、かつ最も強力な効果である。複数の活動が組み合わさった結果が、個々の部分の合計、あるいは積よりも大きくなる状態を指す。「全体は部分の総和に勝る」という原則の究極形である。マーケティング活動が相互に補強し合うことで、非線形的な、時には指数関数的な成果がもたらされる。
この典型例が、マーケティング効果研究の権威であるレス・ビネ(Les Binet)氏が提唱するモデルである。長期的なブランド構築活動が、ターゲットオーディエンスの心の中に製品やサービスに対するポジティブな感情的素地を育む。そして、その「準備が整った」オーディエンスに対して、短期的なパフォーマンス重視の刈り取り型広告が投下されることで、購買へと転換させる。それぞれの活動を単独で実施した場合の成果は限定的かもしれないが、両者を戦略的に組み合わせることで、互いが互いを増幅させ、予測をはるかに超える成果を生み出すのである。
この3つの効果の分類は、単なる学術的な定義分けではない。むしろ、あるマーケティング組織がどのレベルの効果を前提として戦略を構築し、成果を測定しているかは、その組織の戦略的成熟度を直接的に示す指標となる。日々のレポートが加算的効果の報告に終始している組織は、自らのビジネスにおける最も強力な価値創造の機会、すなわち相乗効果を意図的に(あるいは無意識に)無視している状態にある。これは単なる測定上のギャップではなく、競合に対する脆弱性をもたらす戦略的な死角に他ならない。
この加算的なモデルが広く普及している背景には、その「認知的な容易さ」と「経路依存性」がある。ラストクリックアトリビューションは理解しやすく、導入も容易であり、そして何より、広告予算の大部分を消費する巨大プラットフォームがデフォルトで提供する指標である 。これにより、「プラットフォーム上で費やしたドルが、直接的なROIを生んだ」という単純明快なストーリーが完成する。この構造は、マーケターの思考をプラットフォーム内に留め、チャネル横断的な相乗効果から目を逸らさせる強力なフィードバックループを生み出す。このサイクルを断ち切るためには、単に新しいダッシュボードを導入するだけでは不十分であり、経営層からのトップダウンによる意図的な戦略転換が不可欠となる。
測定モデルの批判的評価:欠陥のある単純さから全体論的な真実へ
マーケティングの成果が相乗的であるという事実を認識した上で、次に問われるべきは「それをいかにして測定するか」である。このセクションでは、マーケターが日常的に使用する測定モデルを解体し、それぞれがどのような前提に基づいているのか、そしてどの効果モデル(加算的、乗算的、相乗的)に対応するのかを明らかにする。
加算的 worldview:ラストクリックの専制
マーケティング測定の世界で長らく支配的な地位を占めてきたのが、ラストクリックアトリビューションをはじめとするシングルタッチアトリビューションモデルである。これらのモデルは、コンバージョン直前の最後の接点に成果の100%を帰属させる 。例えば、ユーザーがSNS広告、記事広告、検索広告の順に接触し、最終的に商品を購入した場合、ラストクリックモデルでは検索広告のみが成果として評価され、それ以前のすべてのタッチポイントは無視される。
このモデルがなぜこれほどまでに普及し、今なお多くの現場で使われ続けているのか。その理由は、その圧倒的な「単純さ」にある。理解しやすく、主要な広告プラットフォームの標準機能として提供されているため、追加の投資や専門知識なしに利用できる 。これにより、マーケターは「この広告にこれだけ投下して、これだけのコンバージョンがあった」という、因果関係が明確であるかのような、心地よい(しかし誤った)手応えを得ることができる。
しかし、その単純さは諸刃の剣である。ラストクリックモデルは、顧客が購買に至るまでの複雑な意思決定プロセスを完全に無視し、ブランド認知や比較検討といった重要な初期・中間段階の貢献をゼロと評価する。これは、マーケティング活動の全体像を著しく歪め、短期的な刈り取り施策への過剰投資と、長期的なブランド構築への過小投資を構造的に生み出す「専制」とも言える状況を作り出す。
相乗効果への道のり:マルチタッチアトリビューション(MTA)の約束と危険性
ラストクリックモデルの限界が広く認識されるにつれて、その対案として登場したのがマルチタッチアトリビューション(MTA)である。MTAは、コンバージョンに至るまでの顧客の全行程(カスタマージャーニー)を追跡し、複数のタッチポイントに貢献度を分配しようとする試みであり、哲学的には大きな前進と言える。
MTAには、貢献度の分配方法によっていくつかのモデルが存在する。
- 線形モデル: 最もシンプルなMTAモデルで、コンバージョン経路上のすべてのタッチポイントに均等に貢献度を割り当てる。分析を始めたばかりの組織にとって、どのチャネルが貢献しているかを大まかに把握するのに適している。
- 減衰モデル: 時間の経過とともに貢献度を割り引くモデル。コンバージョンに近いタッチポイントほど高く評価される。
- U字型モデル: 最初のタッチポイントと最後のタッチポイントにそれぞれ高い貢献度(例:各30%)を割り当て、残りを中間のタッチポイントに分配する。認知のきっかけとコンバージョンの決定打を重視する考え方に基づいている。
MTAを導入することで、マーケターはラストクリックでは見えなかったジャーニー全体の貢献を可視化し、より精緻な予算配分を目指すことができる 。しかし、MTAの導入と運用は決して容易ではない。
- 実装の複雑性: まず、追跡すべきタッチポイントを定義し、明確な目標を設定する必要がある。その上で、WebサイトへのJavaScriptコードの埋め込みやCRMとの連携など、高度なデータ収集基盤の構築が不可欠となる。
- 組織的な変革: MTAの導入は、ツールだけの問題ではない。チャネルごとのサイロ化した思考から脱却し、チーム全体で共通のKPIを持ち、ジャーニー全体を俯瞰する文化へと変革することが求められる。関係者全員がMTAの概念とそれがもたらす意味を正しく理解するための啓蒙活動も欠かせない。
- 技術的な脆弱性: MTAの最大の弱点は、その測定基盤がCookieやデバイスIDといったユーザーレベルの識別子に依存している点にある。世界的なプライバシー保護強化の流れの中で、これらの識別子の利用はますます困難になっており、MTAの有効性そのものが脅かされている。これは、後述するメディアミックスモデリング(MMM)との決定的な違いである。
真の相乗効果の捕捉:メディアミックスモデリング(MMM)の力
ラストクリックが「加算的」、MTAが「相乗効果への試み」であるとすれば、戦略レベルで真の相乗効果を捉えるための現時点でのゴールドスタンダードが、メディアミックスモデリング(MMM)である。
MMMの仕組み
MMMは、MTAのような個々のユーザーを追跡するボトムアップ型のアプローチとは対照的に、トップダウン型の統計分析手法である。週次や日次の売上、各チャネルの広告出稿量、プロモーション履歴といった集計された時系列データを用いて、各マーケティング活動が最終的なKPI(売上など)にどれだけ貢献したかを統計的に分解する。
MTAに対するMMMの主な優位性
- 全体論的なスコープ: MMMは、オンライン広告だけでなく、テレビCM、新聞、ラジオといったオフラインメディアの効果も同一のモデルで分析できる。さらに、季節性、景気動向、競合の活動、さらには天候といった、マーケティング以外の外部要因が成果に与える影響も考慮に入れることができる 。これは、オンラインのタッチポイントに限定されがちなMTAにはない大きな利点である。
- プライバシー保護への耐性: MMMはユーザーレベルの個人データではなく、集計データを使用するため、Cookie規制のようなプライバシー保護強化の動きに影響を受けない。これにより、将来にわたって安定した測定が可能となる、未来志向のフレームワークである。
- 未来志向の戦略的ツール: MMMは、過去の貢献度を分析するだけのツールではない。その真価は、未来を予測するためのシミュレーションエンジンとしての機能にある。構築されたモデルを用いて、「テレビCMの予算を10%増やし、Web広告の予算を5%減らした場合、売上はどう変化するか?」といった様々な予算配分シナリオをシミュレーションし、ROIを最大化する最適なメディアミックスを導き出すことができる 。これにより、マーケティングの議論を、経営層が理解できる財務的な言語へと翻訳することが可能になる。
もちろん、MMMも万能ではない。分析には最低でも2年以上の長期間にわたる一貫したデータが必要であり、モデル構築には高度な統計的専門知識が求められるため、リソースと時間を要するプロジェクトとなる。
測定モデルの進化は、単なる技術的な進歩ではない。それは、マーケティング組織が自らに問いかける「問いの質」の進化そのものである。ラストクリックは「どのチャネルがこの売上の手柄を立てたか?」と問う。MTAは「我々のデジタルチャネルは、この売上にどのように貢献したか?」と問う。そしてMMMは、「我々のマーケティングポートフォリオ全体が、市場の外部要因と連動して、いかに事業のコアKPIを動かしているのか?そして、未来の成長を最大化するために、我々はどう投資すべきか?」と問う。選択する測定モデルが、組織の戦略的対話のレベルを規定するのである。
この文脈でMTAを捉え直すと、その歴史的役割は「必要だが、十分ではなかった」進化の段階であったと言える。MTAはシングルタッチアトリビューションの欠陥を正しく指摘し、ジャーニー思考の重要性を啓蒙した。しかし、その技術的基盤であったユーザーレベルのトラッキングは、時代の潮流と衝突することになった。かつては粒度の粗さが弱点と見なされたMMMの集計データアプローチが、皮肉にも今やその最大の戦略的強みとなっている。今後のマーケティング測定は二極化するだろう。戦術レベルのリアルタイム最適化は、引き続きプラットフォームが提供する加算的なデータに依存する。しかし、戦略レベルの長期的な予算配分は、相乗効果を捉えるMMMのような集計モデルにますます依存していくことになる。
相乗効果の戦略的エンジン:ブランドとパフォーマンスの統合
測定モデルが「何を」測るかのツールであるならば、戦略は「どのようにして」相乗効果を生み出すかの設計図である。このセクションでは、測定モデルの議論を具体的な戦略実行へと結びつける。相乗効果は偶然の産物ではなく、バランスの取れたマーケティング戦略がもたらす必然的な帰結であることを明らかにする。
マーケティングの2つの速度:長期的ブランド構築 vs. 短期的セールスアクティベーション
相乗効果を生み出すための戦略的基盤として、マーケティング効果研究の第一人者であるレス・ビネとピーター・フィールドの研究は欠かすことができない。彼らは、マーケティング活動には明確に異なる2つの機能、2つの「速度」が存在すると主張する。
- ブランド構築(長期的): この活動の目的は、現時点では購買意欲がない「将来の顧客」を含む広範なオーディエンスの心の中に、ブランドに対する永続的な「心的利用可能性(Mental Availability)」とポジティブな感情的連想を築くことである。ここで用いられるメッセージは、理性的ではなく感情に訴えかけ、記憶に残りやすく、エンターテイメント性が高いものとなる 。これは市場全体を「温める」ための活動であり、「ショーマンシップ」に例えられる。
- セールスアクティベーション(短期的): こちらの目的は、すでに市場内で購買を検討している「現在の顧客」が持つ需要を、即時の売上へと転換させることである。ターゲットは狭く、メッセージは製品の利点や価格、購入方法といった理性的で情報量の多い、行動喚起を促すものとなる 。これはブランド構築によって生まれた需要を「刈り取る」活動であり、「セールスマンシップ」に例えられる。
ビネとフィールドが強調する極めて重要な点は、これら2つの活動は目的もターゲットもメッセージも異なるため、単一の広告で両方の役割を同時に果たそうとすべきではないということである 。ポイント・オブ・パーチェス(購買時点)でブランドストーリーを語ろうとするのは、それぞれの仕事の邪魔をするだけの誤った試みなのである。
60:40ルール:相乗的成長への実証済み青写真
ビネとフィールドは、1,000件以上のキャンペーン事例の長期的な分析に基づき、長期的な利益成長を最大化するための予算配分の黄金比として「60:40ルール」を提唱した。これは、マーケティング予算の約60%を長期的なブランド構築に、残りの40%を短期的なセールスアクティベーションに投下するというガイドラインである。
この比率がなぜ相乗効果を生むのか。そのメカニズムは明確である。ブランド構築活動が、セールスアクティベーション活動の効率を劇的に向上させるからだ。強力なブランドが存在すれば、人々はすでにそのブランドに対して「温められた」状態にある。その結果、パフォーマンス広告のクリック率は高まり、コンバージョン率は改善し、顧客獲得単価は低下する 。これこそが、第1部で述べた「乗数効果」の実践的な現れである。
もちろん、この60:40という比率は万能薬ではなく、あくまで出発点である。B2Bのように検討期間が長く合理的な判断が重視される業界ではアクティベーションの比率が高まる可能性があり、市場の状況やブランドのライフサイクルに応じて柔軟に調整されるべきである。
特に日本市場の文脈で注意すべき点として、ビネが「メディア・ファースト・トラップ」と呼ぶ現象が指摘されている。これは、ブランド戦略が固まる前に、まずテレビCMの枠などのメディアバイイングを先行させてしまう慣行である。その結果、戦略なきまま広告枠を埋めるためだけのクリエイティブが量産され、莫大な広告費が「記憶に残らないノイズ」へと変わり、長期的なブランド資産の構築が疎かになるという問題である 。この罠を回避し、60:40の原則に立ち返ることが、日本企業にとっての喫緊の課題と言える。
相乗効果の証拠:成功と失敗のケーススタディ
理論を現実に落とし込むために、具体的な事例を見ていこう。
成功事例
- 消費財メーカーの事例: ある企業は、テレビCMとデジタル広告の相乗効果を定量化するためにMMMを導入した。分析の結果、テレビCM放映直後にデジタル広告の予算を増額する運用を行ったところ、全体の売上が前年比で15%増加した。MMMにより、「テレビCM単体の効果」だけでなく、「テレビCMがデジタル広告の効果を高める」という掛け算の効果を定量的に証明し、予算配分を最適化できた。
- 小売業の事例: ある小売企業は、オフラインの店舗売上データとオンラインのECサイトのデータを統合してMMMを構築した。その結果、チラシが店舗への来店を促進し、さらにその来店客が後日ECサイトで追加購入を行うという、オフラインとオンラインをまたぐ相乗効果のパターンを発見。統合的なプロモーション戦略の立案に成功した。
- Eコマース企業の事例: Google広告が売上の50%に貢献していることがわかっていた企業が、Facebookのリマーケティング(初期の需要を刈り取るアクティベーション戦術)を強化したところ、全体の売上が20%増加した。これは、需要創出チャネルと刈り取りチャネルの連携が成功した好例である。
失敗から学ぶ教訓
- データとモデルの欠陥: ある企業のMMMは、広告効果を過大に評価するという誤りを犯した。その原因は、モデルに「在庫切れ」の期間という重要な外部要因のデータが含まれていなかったためである 。また、別の企業は、競合の活動や経済指標といった外部要因をモデルに組み込まなかったため、予測精度が著しく低下し、景気後退局面での判断を誤った。
- 戦略と測定のミスマッチ: ある金融サービス企業は、リードタイムが非常に長い商品を扱っていたにもかかわらず、ブランド構築を目的とするテレビCMの効果を、ごく短期的な入会者数のみで評価してしまった。その結果、長期的なブランドロイヤルティ向上というCMの真の価値を捉えることができず、投資判断を誤った。
これらの事例が示すのは、60:40ルールが単なる予算配分のガイドラインではなく、「将来の顧客を創造しながら、現在の顧客を収穫する」という戦略的コミットメントであるという事実である。ブランド構築への60%の投資は、伝統的な意味での「経費」ではない。それは、将来の顧客獲得コストを低減するための「投資」であり、市場を単に獲得する(Market-Capturing)だけでなく、市場そのものを創造する(Market-Making)ための戦略的行為なのである。
そして、この相乗効果を前提とした戦略実行における最大の障壁は、多くの場合、技術的な問題ではなく、組織内の政治と報告体制である。長期的なブランド価値を訴えるCMO(最高マーケティング責任者)と、短期的で証明可能なROIを要求するCFO(最高財務責任者)との間の緊張関係は、多くの企業で見られる典型的な対立構造だ。
この根深い対立を解消する究極の「政治的ツール」こそが、MMMである。MMMは、ブランド構築という「感情的なフリムフラム(戯言)」が、長期的な売上にどれだけの財務的インパクトを与えるかをモデル化する。これにより、CMOはブランドの価値をCFOが理解できる合理的な財務言語に翻訳し、組織全体の合意形成を図り、60%のブランド投資予算を確保することが可能になる。MMMの導入は、単なるマーケティング部門の技術的アップグレードではない。それは、組織全体の財務的・政治的力学を再構築し、よりバランスの取れた、収益性の高い長期的な視点を根付かせるための、全社的な戦略イニシアチブなのである。
相乗効果を駆動するマーケティングエコシステムの設計と実装
これまでの議論を踏まえ、この最終セクションでは、本レポートで得られた知見を具体的な行動へと移すための実践的なロードマップを提示する。
乗数効果を証明するための段階的アプローチ
相乗効果の価値を組織内で経験的に証明するためには、明確な実験計画が不可欠である。以下に示す4段階のテスト計画は、あらゆる組織が自社の状況に合わせて応用できるフレームワークである。
- テスト1:ブランド効果の分離測定 まず、ブランドキャンペーンのみを単独で実施する。その際、売上やコンバージョンといった短期的な指標への直接的なインパクトを測定する。この段階では、短期的成果は低く出ることが予想されるが、これがベースラインとなる。
- テスト2:ダイレクトレスポンス効果の分離測定 次に、ダイレクトレスポンス(刈り取り型)キャンペーンのみを単独で実施する。成果は、プラットフォームが提供する標準的なツール(ラストクリックなど、加算的なモデル)を用いて測定する。これにより、各刈り取り施策の単独でのパフォーマンスが明らかになる。
- テスト3:組み合わせによる効果測定(乗数効果の検証) ブランドキャンペーンとダイレクトレスポンスキャンペーンを同時に実施する。ここでの重要な点は、成果測定にMMMを用いることである。目的は、ブランドキャンペーンがダイレクトレスポンスキャンペーンの成果を単に足し合わせるのではなく、その効果を「乗算的に」高めているかどうかを確認することにある。複合的なインパクトが、個々の合計値を上回れば、乗数効果が証明される。
- テスト4:規模拡大による効果測定(相乗効果の検証) 最後に、両キャンペーンをより大きな規模で同時に展開する。ここで注目すべきは、非線形的なリターンの発生である。ブランドキャンペーンがダイレクトレスポンスのパフォーマンスを単に乗算的に高めるだけでなく、根本的に向上させ、投資額の増加に対して成果が指数関数的に伸びるような現象が見られれば、それは真の「相乗効果」が生まれている証拠となる。
この段階的なアプローチにより、マーケティングリーダーは、相乗効果という抽象的な概念を、具体的なデータと数値に基づいた説得力のあるストーリーとして、経営層や他部門に提示することができる。
メディアミックスモデリング(MMM)の実践ガイド
MMMの導入を検討している組織のために、その実践的な手順を以下に示す。
- ステップ1:目的と分析ロジックの定義 まず、「ROIを最大化する最適な予算配分は何か?」「テレビCMはWeb広告にどの程度影響を与えているか?」といった、ビジネス上の問いを明確に定義する。その目的に応じて、重回帰分析やパス解析といった適切な統計分析ロジックを選択する。
- ステップ2:変数の特定とデータ収集 次に、定義したKPIに影響を与えうる全ての要因(変数)を洗い出す。これには、自社の全てのマーケティング活動(オンライン・オフラインの施策、出稿量、費用)だけでなく、競合の広告出稿、季節性、経済指標、プロモーションといった外部要因も含まれる 。これらの変数について、最低でも2〜3年分の一貫性のある粒度(週次または日次)の時系列データを収集する 。データの質と量が、モデルの精度を左右する。
- ステップ3:モデルの構築、検証、改良 収集したデータを用いて、統計モデルを構築する。これは、データサイエンティストと、事業内容を深く理解するドメインエキスパート(マーケターなど)との緊密な協力が不可欠な、反復的なプロセスである。構築されたモデルは、統計的な妥当性だけでなく、ビジネスの観点から見て論理的かどうかが厳しく検証される必要がある。MMMは一度構築して終わりではなく、市場環境の変化に対応するために、定期的(例:四半期ごと、年次)に見直しと改良を重ねていく必要がある。
- ステップ4:シミュレーションと最適化 検証済みのモデルを用いて、「What-if」シナリオ分析を実行する。様々な予算配分パターンをシミュレーションし、KPIへのインパクトを予測することで、戦略的な予算配分計画の策定を支援する 。これにより、議論は過去の分析から未来の創造へと移行する。
現代のマーケティングリーダーに求められる戦略的責務
本レポートの分析を総括し、CMOをはじめとするマーケティングリーダーが取るべき行動を、3つの戦略的責務として以下に提示する。
- ポートフォリオ思考の徹底 チャネルを個別のサイロとして管理するのをやめ、マーケティング予算を一つの「投資ポートフォリオ」として捉えるべきである。個々のチャネルのROIではなく、ポートフォリオ全体の相乗的なリターンを最大化することを目標としなければならない。
- 測定が容易なものではなく、重要なものを測定する 組織の測定能力を、ラストクリックという成熟度の低い段階から、MMMという高次の段階へと意図的に引き上げる必要がある。全体像を把握するためのツールと人材への投資を惜しんではならない。それはコストではなく、より良い意思決定を通じて何倍ものリターンを生む戦略的投資である。
- 「バイリンガル・リーダー」になる 現代のマーケティングリーダーは、ブランドの言語(感情、物語、クリエイティブ)と、ファイナンスの言語(ROI、インクリメンタリティ、利益成長)の両方を流暢に話せる「バイリンガル」でなければならない。そして、MMMをその「翻訳機」として活用し、組織全体をバランスの取れた長期的な成長戦略の下に結束させるべきである。
- 戦略的な忍耐を貫く 短期的な成果のみを求める社内外からの圧力に抵抗し、未来の成長エンジンであるブランドへの60%の投資を守り抜かなければならない。マーケターは消費者よりも早く自社のクリエイティブに飽きてしまう、という指摘があるように、ブランドキャンペーンが効果を発揮するには時間が必要である 。構築したモデルを用いてその長期的な価値を証明し、「戦略的な忍耐」の重要性を組織に根付かせることが、リーダーの重要な責務である。
参考サイト
MARTECH「Marketing results don’t add. They multiply and synergize.」

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。



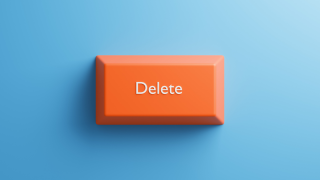
-2025-09-05T151236.591-320x180.png)






-7-320x180.png)



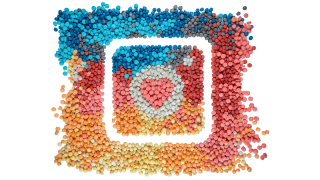


-2025-07-04T164514.730.png)


-2025-07-04T152222.677-120x68.png)
-82-120x68.png)