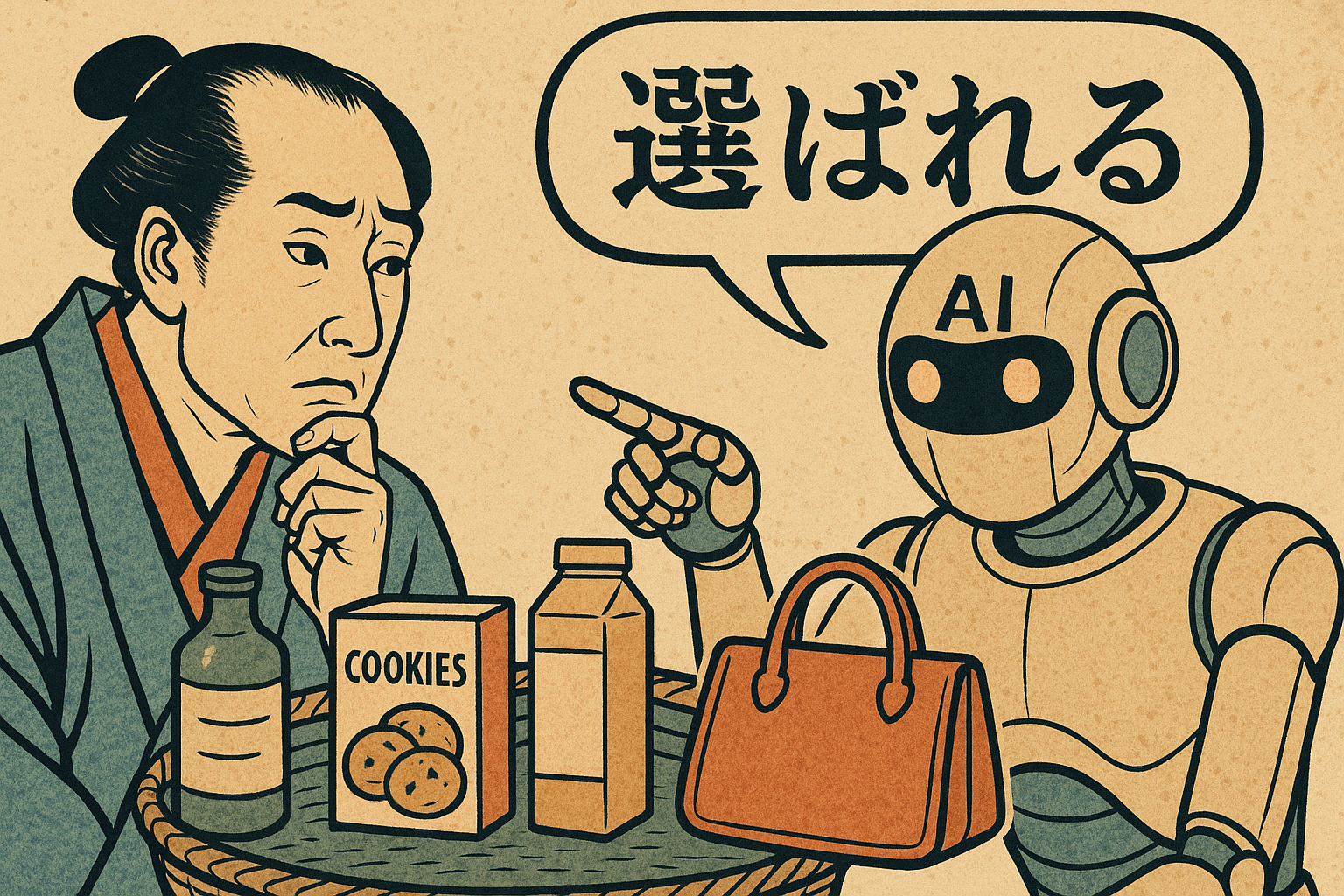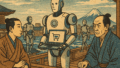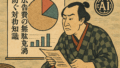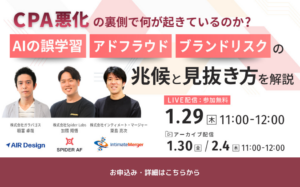「人が選ぶ」から「AIが選ぶ」へ
検索して、比較して、カートに入れて購入する──長く続いてきたオンラインショッピングの流れが、静かに書き換わりつつあります。 これからは、ユーザー本人ではなく、自分専用のAIエージェントが条件に合う商品を探し、比較し、ときには自動で注文まで進める時代が見えています。
こうした流れは「エージェントコマース」と呼ばれ、AIショッピングエージェントが、新しい「売り場の入口」として存在感を高めています。 デジタルマーケティング担当者にとって重要になるのは、人間だけでなく「AIにとっても選びやすい商品・ブランド」を設計することです。
本記事では、エージェントコマース元年ともいえる今のタイミングで、 マーケターが押さえておきたい基本概念から、具体的な施策例、組織としての進め方までを整理します。
- エージェントコマースの全体像と、従来ECとの違いをイメージできるようにする
- AIショッピングエージェントに「選ばれやすい」商品・ブランドの条件を理解する
- 自社で始められる具体的なアクションプランを持ち帰る
エージェントコマースとは何か
エージェントコマースは、AIエージェントがユーザーの代わりに調べ、比較し、購入までを支援するショッピング体験です。 単なるチャットボットではなく、「買い物を任せられるパートナー」として機能する点に特徴があります。
エージェントコマースの基本イメージ
ユーザーは、AIエージェントに「条件」と「意図」を伝えるだけです。 例えば、「敏感肌向けで、価格はこのくらい、レビュー評価もある程度高い日焼け止めを探して」といった要望に対し、 エージェントが複数のECサイトや情報源を横断し、候補を絞り込んでくれます。
従来のEC・チャットボットとの違い
- ユーザー主導からエージェント主導へ:従来はユーザーが検索ワードを考え、絞り込み条件を操作していましたが、今後はAIが条件設計と比較を担います。
- 対話から「実行」までをカバー:チャットボットは質問への回答が中心でしたが、エージェントは「商品選定〜決済〜配送手配」までの一連のタスクを扱うようになります。
- 1画面のランキングから「1回答の推薦」へ:検索結果の順位ではなく、「AIの回答に載るかどうか」が重要な競争軸になります。
「検索結果の上位を目指すSEOだけでなく、エージェントの回答に載るための“AI向けプレゼンス設計”が必要になりそうだな……」
エージェントコマースがもたらす価値
エージェントコマースは、ユーザー体験だけでなく、マーケティングや事業側にもさまざまな可能性を広げます。 ここでは、マーケター目線での利点を整理します。
ユーザー体験の向上とファン化のきっかけ
- 条件に合う商品が見つかりやすくなる:用途や好みを自然言語で伝えるだけで、AIが候補を整理してくれます。
- 比較の手間が大きく減る:スペック・価格・レビューなどをまとめて比較したうえで、おすすめを提案できます。
- 継続購入がしやすくなる:定期購入やリピートの条件もAI側で管理できるため、「うっかり切らした」が減ります。
ブランド・事業者側のメリット
- 新規接点の創出:自社サイトに来訪していないユーザーにも、AIエージェントの回答を通じて商品が紹介される可能性があります。
- 意図ベースのマッチング:キーワードではなく「解決したい課題」ベースで商品とユーザーが結びつきやすくなります。
- 中長期的な関係づくり:AIエージェントがユーザーの好みや履歴を理解することで、長期的な推奨関係が築かれる可能性があります。
エージェントコマースでは、単に商品ページが存在するだけでは不十分です。 AIエージェントが「この条件なら、このブランド/この商品がふさわしい」と判断しやすい情報設計になっているかが重要になります。
- ユーザーの目的・利用シーンと結びついた説明になっているか
- 仕様・特徴・制約が、AIにとって解釈しやすい形で記述されているか
- レビューやQ&Aなど、第三者の声も適切に整理されているか
AIに「選ばれる」ための実践的な応用方法
ここからは、デジタルマーケティング担当者が現場で取り組みやすい施策例を中心に、 エージェントコマース時代の「商品・データ・コンテンツ」の整え方を具体的に見ていきます。
プロダクトデータを「AIが読み取りやすい言語」にする
エージェントコマースでは、プロダクトデータそのものが、AIにとっての「素材」になります。 情報が曖昧だったり、項目が抜けていたりすると、候補から外れてしまうリスクがあります。
- 商品属性(サイズ・容量・素材・対応機種など)を整理し、抜け漏れを減らす
- 用途・ターゲット・利用シーンを明確にテキストで記述する
- スペックだけでなく、「どんな悩みを解決するか」を文章で補足する
- 最新情報(リニューアル内容、仕様変更など)が一元的に更新される仕組みを整える
レビュー・Q&A・UGCを整理して「信頼シグナル」を高める
AIエージェントは、公式情報だけでなく、レビューやQ&A、ユーザー生成コンテンツ(UGC)なども参考にしながら判断します。 こうした情報を計画的に整えることで、「安心して推薦できる商品」として認識されやすくなります。
- よくある質問をQ&A形式で整理し、商品ページやヘルプにまとめておく
- レビュー依頼のタイミングや導線を見直し、適切な量と質のレビューを集める
- レビューの中で繰り返し出てくるキーワードを把握し、商品説明文にも反映する
- 実際の利用シーンが伝わる写真やストーリーを、コンテンツとして活用する
ブランドの信頼・ポリシー情報を「見つけやすく」する
AIエージェントは、商品だけでなく「そのブランドを推薦してよいか」という観点でも情報を評価します。 返品・交換ルールやサポート体制などが分かりやすいほど、ユーザーに安心して提案しやすくなります。
- 返品・交換・保証に関するポリシーを、簡潔で分かりやすい文章でまとめる
- サポート窓口(チャット・メール・電話など)の情報を整理して掲載する
- 安全性・品質基準・認証情報などがあれば、ユーザーにもAIにも伝わる形で記載する
価格・在庫・納期などの「リアルタイム性」を意識する
エージェントコマースでは、「今買えるか」「いつ届くか」といった情報も重要な判断材料になります。 データが古いと、AIは別の商品を推薦するかもしれません。
- 在庫・価格・納期などの情報を、できるだけ最新状態で提供できるようにする
- 欠品時・再入荷時の扱い方(代替商品の提案など)をルール化する
- セールやキャンペーン情報を構造的に管理し、AIにも認識されやすくする
エージェント向けの「商品ガイド」を用意する
今後、ブランド側が自社データをエージェントに提供するための標準的な仕組みが増えていくと考えられます。 そのときに備え、「AIが読みに来る前提のガイド」を用意しておくと、対応がスムーズになります。
- ブランドの世界観・ミッション・大切にしている価値
- 主力商品のカテゴリごとの特徴と、向いているユーザー像
- よくある比較軸(価格帯・グレード・用途など)と、その整理の仕方
- ユーザーに誤解してほしくない注意点や、非推奨の使い方
エージェントコマースへの第一歩:導入のステップ
「何から手を付ければよいか分からない」という声も多いテーマです。 ここでは、マーケティング担当者が社内を巻き込みながら進めることを想定した、現実的なステップ案を紹介します。
まずは、主要なAIアシスタントや検索サービスで、自社商品がどのように扱われているかを確認します。 自分で実際に問いかけてみるのが一番早い方法です。
- 自社ブランド名+代表的なニーズで検索・質問してみる
- 競合ブランドがどのように紹介されているかもあわせて確認する
エージェントコマースの対応には、マーケティングだけでなく、EC運営、データ・IT、カスタマーサポートなどの連携が欠かせません。
- マーケ/EC/システム/CSなどから少人数のタスクフォースを組成する
- 月1回などの定例で、「AIから見た商品・ブランド」をテーマに議論する
カタログ情報・仕様書・販売ページなどがバラバラになっている場合は、 まず「どの情報が最新か」を明確にすることから始めます。
- 商品マスタの整備(属性・カテゴリ・タグの見直し)
- 説明文やFAQの「正」の版をどこに置くか、管理ルールを決める
いきなり全商品を対象にするのではなく、代表的な1カテゴリを選んで試すと、学びが得やすくなります。
- 売上規模・戦略上の重要度・データの整備状況などから対象カテゴリを決める
- そのカテゴリに限って「AIに選ばれるための情報設計」を重点的に実施する
エージェントコマース専用の指標はまだ発展途上ですが、 まずはシンプルな観点から「変化」を追っていくことが現実的です。
- AIアシスタントでのブランド・商品言及数の変化
- 「〜におすすめの商品は?」などの質問に対する自社露出の有無
- エージェント起点と思われる流入や問い合わせのケースを社内で共有する
パイロットでうまくいった情報設計・レビュー施策・FAQの作り方などをテンプレート化し、 他カテゴリや他ブランドにも広げていきます。
- 「AIに伝わりやすい説明文」のサンプルを、社内の共通フォーマットにする
- プロダクトチーム・営業・カスタマーサポートとも連携し、全社での共通言語にしていく
エージェントコマースのこれから
エージェントコマースは、まだ始まりつつある領域です。 しかし、各社の取り組みや技術の進化を見ると、マーケターの仕事の前提が数年単位で変わっていく可能性があります。
パーソナルエージェントが「日常の購買」を支える
ひとり一体以上のパーソナルAIエージェントが、生活や仕事のあらゆるシーンで動くようになると、 日用品やサブスクリプション、業務用品の購買は、ますます自動化されていくと考えられます。
- 消耗品の残量や使用頻度から、自動的に補充タイミングを提案・実行する
- ライフスタイルの変化(引っ越し・子どもの成長・仕事の変化など)に合わせて、必要な商品を再提案する
- ユーザーの価値観(環境配慮・国産志向・デザイン性など)に沿った候補を長期的に学習する
「AIに話しかける」こと自体がマーケティングチャネルになる
検索窓だけでなく、チャット・音声・アプリ内のAIなど、 ユーザーがAIに話しかけるあらゆる場が、新しいマーケティングチャネルになります。
これに伴い、「どんな言い方で聞かれたときに、自社の商品が候補に挙がってほしいか」を逆算し、 コンテンツやプロダクトメッセージを設計する発想が重要になります。
マーケターの役割は「AIとの共創」へ
エージェントコマースの世界では、AIが多くのオペレーションを担う一方で、 人間のマーケターには、より上流の役割が求められます。
- 自社ブランドの価値やストーリーを、AIにとっても理解しやすい形で定義する
- どのようなユーザーに、どのような場面で推薦してほしいかを設計する
- AIを通じて起きている購買や反応を観察し、プロダクト開発や体験設計に活かす
つまり、「AIと共同で市場を開拓する」という視点が、今後のマーケターにとって大きなテーマになっていくでしょう。
エージェントコマース元年に、今できる準備
エージェントコマースは、まだ「これが正解」というパターンが固まっているわけではありません。 だからこそ、早いタイミングで試行錯誤を始めたチームほど、知見とアドバンテージを蓄積しやすくなります。
- エージェントコマースでは、AIショッピングエージェントが新しい「売り場の入口」になる
- AIに「選ばれる」ためには、プロダクトデータ・レビュー・ブランド情報の整え方が重要になる
- まずは1カテゴリから、商品情報とFAQの整備・AIでの露出チェックなどを試してみる
- マーケターの役割は、AIと協力してユーザーにふさわしい選択肢を届ける方向へと広がっていく
いきなり完璧を目指す必要はありません。 プロダクトページの一文を見直すことや、よくある質問を整理することも、立派な第一歩です。 明日の施策のうち、どれか一つを「AIに選ばれる商品づくり」という視点で見直してみるところから始めてみてください。
よくある質問
すでに一部のサービスでは、AIを通じた商品検索や、その場での購入体験が始まっています。 一方で、すべてのユーザーがAIエージェント経由で買い物をする世界には、まだ時間があります。 その意味では、「今は本格化に向けた準備期間」と捉えるとよいでしょう。
関係があります。むしろ、規模が小さいブランドほど、AIエージェントを通じて新しいユーザーに見つけてもらえる機会が生まれやすくなります。 そのためにも、商品情報やブランドストーリーを丁寧に整えておくことが重要です。
広告やSNSが不要になるというよりも、「役割が変わる」と考えるほうが現実的です。 これまで以上に、ブランドの世界観や価値観、ユーザーの声を伝える場として機能し、 その情報がAIエージェントの判断にも影響する可能性があります。
おすすめは、「主要商品の説明文とFAQの見直し」です。 ユーザーがよく口にするニーズや質問を洗い出し、それに答える形で商品説明やQ&Aを整えることで、 AIエージェントにとっても理解しやすい情報になります。
すべての企業が独自のAIエージェントを用意する必要はありませんが、 自社サイト内で質問に答えるチャット型のサポートや、商品提案エージェントを用意することは有力な選択肢になります。 まずは既存のツールやプラットフォームを活用し、小さく試していくとよいでしょう。
エージェントコマースでは、ユーザーがAIに多くを任せる分、ブランド側にはより誠実な情報提供が求められます。 誇張表現を控え、リスクや制約条件も含めて正確な情報を提供することが、長期的な信頼につながります。 社内の法務・コンプライアンス担当とも連携しながら、ガイドラインを整備していくことが大切です。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。









-7-320x180.png)