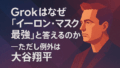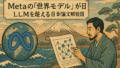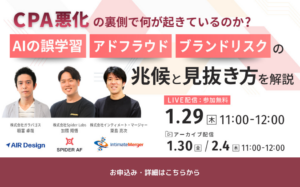ここ数週間、AI業界では「エージェント」をキーワードに大きなニュースが続いています。 Googleは最新モデルGemini 3を発表し、企業向けのGemini Enterpriseや 日常業務を自動化するGemini Agentなど、エージェント前提のプラットフォームを拡張しています。
一方、OpenAIはブラウザ操作まで行うAIエージェントOpenAI Operatorを起点に、 ChatGPTエージェントやAgents APIなど、より広いエコシステムへと展開しつつあります。
・OpenAI:ブラウザや外部ツールをまたいで動く「汎用エージェント+チャットエージェント」
どちらも「人の代わりに考えて動くAI」という点では似ていますが、
組織のデータにどうつなげるか・どの業務をどこまで任せるかという設計思想には違いがあります。
本記事では、「今週のAIニュース」という切り口で両者の動きを整理しつつ、 デジタルマーケティング担当者が実務でどう向き合うべきかを、できるだけ平易な言葉で解説していきます。
「それぞれのエージェントを使うと、マーケティング業務がどう変わりそうか?」にフォーカスしています。
🧩概要
💡 Snapshot 今週のトピックの全体像
まず、GoogleとOpenAIそれぞれの動きを、マーケター視点でざっくり整理しておきます。
・Gemini Enterpriseとして、社内検索・アシスタント・エージェント基盤を一体提供
・Google Workspaceや各種業務ツールと連携し、ワークフローの自動化を支援
・個人向けには「Gemini Agent」として日常業務の代行にも対応
・フォーム入力・予約・簡単な購買・業務ツール操作など、Web上の繰り返し作業を代行
・ChatGPTエージェントやAgents APIと組み合わせて、より広い自動化エコシステムに発展
・安全性や制御性に配慮したガイドラインを整備
🔍 Gemini Google Gemini 3 / Gemini Enterpriseの特徴
Googleは、最新モデルGemini 3を、開発者向けのVertex AIに加えて、 ビジネスユーザー向けのGemini Enterpriseでも利用できるようにしています。
- マルチモーダル対応:テキストだけでなく、画像やファイルも含めた情報を扱える。
- 長いコンテキスト:長文のドキュメントや会議ログなどをまとめて解析しやすい。
- エージェント前提の設計:ワークフロー自動化や業務代行を想定した機能が組み込まれている。
- Google Workspaceとの連携:Gmail・カレンダー・スプレッドシートなどと自然に接続できる。
マーケティング領域では、「社内データに強い総合アシスタント兼エージェント基盤」として活用を検討しやすいポジションです。
🧠 Operator OpenAI Operatorとエージェントエコシステム
一方のOpenAI Operatorは、ブラウザを人間のように操作することを特徴とするエージェントです。
- ブラウザ操作に特化:クリック・スクロール・入力など、画面上のUIを直接操作。
- Webアプリの横断利用:固定のAPIがなくても、ブラウザ上であれば多くのSaaSにアクセス可能。
- 安全性を考慮した設計:危険な操作を抑制するためのルールや安全機能を用意。
- ChatGPTエージェントとの連携:エージェントAPIやMCP(ツール連携)と組み合わせることで、より柔軟な自動化が可能。
こちらは、「Web上の事務作業や運用作業をまとめて任せられる汎用ワーカー」としての性質が強いといえます。
- Gemini:社内ナレッジや業務データに寄り添う「インハウス寄りエージェント基盤」
- Operator:ブラウザを介してさまざまなツールを操作する「汎用Webワーカー」
- どちらも「AIが仕事を進める」ことを前提にしているが、得意とする文脈が少し異なる。
✅利点
📈 Value マーケターから見たGemini活用の利点
Google Gemini 3とGemini Enterpriseは、マーケティング組織にとって次のような価値をもたらします。
- 社内ナレッジの「横断検索+要約」
キャンペーンの過去資料、レポート、議事録、提案書など、散在しがちな情報を横断的に検索し、 会話形式で整理してもらえます。
「過去1年の●●キャンペーンの学びをまとめて」「この顧客に提案した資料を一覧で出して」のような使い方が想定できます。 - ワークフロー視点でのエージェント設計
ワークスペースや業務アプリと組み合わせることで、「リードが追加されたら要約を作成し、Slackへ投稿」など、 一連の流れをエージェントに任せるイメージで整えやすくなります。 - チーム全体での利用しやすさ
ブラウザベース・ワークスペースベースで提供されるため、エンジニアリングに詳しくないメンバーでも、 比較的スムーズに「AIに仕事を頼む」体験を共有できます。
🧱 Value OpenAI Operator活用の利点
OpenAI Operatorは、マーケターにとって次のような利点があります。
- 「APIがないツール」も含めて自動化しやすい
管理画面しか用意されていない広告ツールや、半分手作業で使っているSaaSであっても、 ブラウザ操作としてまとめて扱える点が特徴です。 - 人のクリック作業を肩代わり
「毎週同じレポートをダウンロードする」「ダッシュボードで数値を確認してスプレッドシートに転記する」 といったルーティン業務を、会話で指示して任せる方向性が見えています。 - 既存のChatGPT利用からの延長線上で考えられる
すでにChatGPTを使っている組織であれば、その延長としてエージェント機能を検討しやすく、 やること・やらないことの線引きも議論しやすいです。
🤝 Combine 両者を組み合わせると見えてくるメリット
実務で考えると、「GeminiかOperatorか」の二択ではなく、 「データに強いGemini」と「Web操作に強いOperator」を役割分担させるという発想も現実的です。
・ターゲットセグメントやメッセージ案の整理
・ワークフロー全体の設計・文書化
・簡単な設定変更や予約操作の自動化
・各種SaaSからのデータ取得や更新
どちらを選ぶかだけでなく、自社の業務フローのどこにどのタイプのエージェントを置くかを設計することで、 現場での納得感を得ながら導入を進めやすくなります。
🛠️応用方法
ここからは、マーケティング担当者が実際に検討しやすい具体的なユースケースを、 GeminiサイドとOperatorサイドそれぞれの視点で紹介します。
📊 Gemini Gemini Enterpriseを「マーケティング司令塔」として使う
Gemini Enterpriseは、社内のドキュメントやワークスペースと連携することで、 マーケティング組織の「司令塔」のような役割を担えます。
- キャンペーン振り返りの要約エージェント
各案件のレポート・会議メモ・ダッシュボードキャプチャをまとめて渡し、 「今回のキャンペーンの学びを3つ」「次回に活かせる改善案を3つ」といった要約を生成。 - 提案書・企画書ドラフト作成
過去の提案書やホワイトペーパーを参照しつつ、 ターゲット・目的・予算を入力すると、構成案とドラフト文を返してくれるエージェント。 - インサイト探索アシスタント
「このセグメントで反応が良かったクリエイティブは?」「直近3か月の傾向は?」 といった問いに対し、関連資料を横断して答えてくれるインサイト探索用エージェント。
🖱️ Operator Operatorで「運用の細かい手」を自動化する
Operatorはブラウザ操作が得意なため、マーケティング現場では次のようなタスクへの応用がイメージできます。
- レポートダウンロードの半自動化
広告プラットフォームや分析ツールにログインし、指定条件でレポートをダウンロードしてストレージに保存する、 といったルーティン作業を、自然言語の指示で任せるイメージです。 - ダッシュボードの定期チェック
一日の開始時に、特定の指標が設定した範囲から大きく外れていないかを確認し、 簡単なサマリーをメッセージで共有するといった用途も考えられます。 - 外部SaaSとの橋渡し
API連携のないWebツールから情報を取得し、別のツールに転記するなど、 いわば「人力RPA」に近い作業を、ある程度エージェントに寄せていくイメージです。
あくまで「こうした方向の自動化が技術的には可能」というイメージとして捉え、 導入時にはセキュリティ担当や情報システム部門と連携しながら検討してください。
🧬 Hybrid Gemini×Operatorのハイブリッド・ワークフロー例
応用編として、両者を組み合わせたハイブリッドなワークフローの例も挙げておきます。
「今月の重点KPI」と「注力すべきチャネル」を整理してもらう。
2)推奨アクションをもとに、担当者ごとのToDoリストを作成。
レポート取得やステータス確認といった定型作業を代行。
4)結果をスプレッドシートやノートに整理し、Geminiに要約を依頼。
このように、「考えるエージェント(Gemini)」と「手を動かすエージェント(Operator)」という役割分担を設計できると、 マーケティング組織全体の仕事の流れを少しずつ変えていくことができます。
📌導入方法
ここでは、GeminiとOperator(および関連エージェント機能)をマーケティング組織に導入するときの、 現実的な進め方をステップ形式で整理します。
🧭 Step 導入ステップのイメージ
-
STEP 1「どの業務をAIに任せたいか」を洗い出す
まずは、現状の業務の中から
・資料作成・要約などの知的作業
・レポート取得や入力などのルーティン作業
を書き出し、どのあたりをエージェントに依頼したいかを検討します。 -
STEP 2Gemini向きか、Operator向きかをざっくり仕分ける
・社内ドキュメントやナレッジの活用 → Gemini Enterpriseの検討軸
・ブラウザ上の繰り返し操作 → OperatorやChatGPTエージェントの検討軸
といった具合に、「どのタイプのエージェントが合いそうか」を整理します。 -
STEP 3情報システム・セキュリティ担当とすり合わせる
データの取り扱いやアクセス権限、ログの管理方法などを、情報システム部門・セキュリティ担当と相談します。
どの範囲なら試験導入できそうか、どの情報は扱わないか、といった線引きを決めておきます。 -
STEP 4小さなパイロットプロジェクトを設定する
いきなり多くの業務を任せるのではなく、
「月次レポートの要約」「特定キャンペーンの資料整理」など、 影響範囲が限定されるテーマで試験運用を始めます。 -
STEP 5成果とリスクの両面を振り返る
・時間削減やアイデア出しの質など、ポジティブな効果
・誤回答や権限設定の難しさなど、懸念点
をチームで共有し、ルールやワークフローを調整します。
🧪 Pilot マーケチーム向けパイロット例
共通して出ている課題・成功要因を整理してもらう。
・その結果をもとに、次四半期の施策の方向性メモを共同で作成。
「ダウンロード〜ファイル保存」までの操作を限定範囲で任せてみる。
・結果の正確性や所要時間、運用上の注意点を記録し、適用範囲の拡張可否を検討。
特にエージェントは、うまく使うと便利な一方で、想定より広い範囲に影響を与えることがあります。
段階的な導入と振り返りのサイクルを意識して進めると安心です。
🔮未来展望
🧬 Evolution 「モデルの性能競争」から「エージェントの体験競争」へ
これまでのAIニュースは、「どのモデルが高性能か」という比較が中心でした。 しかし現在は、Gemini 3やOpenAIのエージェント群のように、「どう業務に組み込まれるか」に焦点が移りつつあります。
- 個々のモデル比較 → 「どのエージェントが業務フローにフィットするか」の比較へ
- 単発のチャット利用 → 継続的に仕事を任せる「AIワーカー」としての利用へ
- PoC中心の活用 → チームや部門単位での本格活用へ
🧩 Org マーケ組織に求められる新しい視点
エージェント前提の世界では、マーケティング担当者にも次のような視点が求められていきそうです。
- 「この業務をAIに任せたらどうなるか?」を常に考える習慣
施策を設計するときに、最初から「人がやる部分」と「AIが支援する部分」を一緒にデザインするイメージです。 - データとワークフローの「棚卸し」
どこに、どんなデータと業務プロセスがあるのかを言語化しておくことで、 エージェント導入の検討がスムーズになります。 - 他部門との連携前提のプロジェクト設計
情報システム・セキュリティ・法務といった部門と協力しながら、エージェント活用を進める役割も増えていきます。
🎯 Strategy 「Google vs OpenAI」をどう見るか
「Gemini vs Operator」という構図はわかりやすい一方で、 実務的には「自社のデータやワークフローにどちらがなじみやすいか」がより重要です。
- Googleサービスやワークスペースが業務の中心 → Gemini側の活用余地が大きくなりやすい。
- さまざまなSaaSをまたぐWeb操作が多い → OperatorやChatGPTエージェントの検討余地が広い。
- 両方のエコシステムを一部ずつ利用し、業務ごとに適材適所で組み合わせる選択肢もある。
いずれにせよ、「このツールが正解」と決め打ちするのではなく、業務やチーム構成に合わせて試しながら調整していく視点が現実的です。
🧾まとめ
今週の「Google Gemini vs OpenAI Operator」のニュースは、 モデルの性能競争というよりも、「どのようにエージェントを業務に組み込むか」という競争が本格化してきたことを象徴しています。
- Gemini 3とGemini Enterpriseは、社内ナレッジや業務データに寄り添うエージェント基盤として位置づけられる。
- OpenAI Operatorは、ブラウザを通じて多様なWebツールを操作する汎用エージェントとして特徴的。
- マーケティング実務では、「戦略・分析はGemini」「実行・運用はOperator」という役割分担も検討できる。
- 導入時には、小さなパイロットと他部門とのすり合わせを通じて、任せる範囲とルールを調整していくことが重要。
- 最終的なゴールは「どのツールを使うか」ではなく、「チーム全体でAIとどう協働するか」の設計にある。
ニュースを追うだけでなく、自社の業務に引きつけて「この流れをどう活かすか」を考えることで、 AIエージェント時代のマーケティング組織づくりが一歩ずつ進んでいきます。
❓FAQ
・社内のドキュメントやワークスペースを横断して活用したい → Gemini Enterpriseから。
・ブラウザ上の繰り返し作業が多く、Webツールの操作を自動化したい → OperatorやChatGPTエージェントから。
まずは「一つのユースケースに対して、一つのエコシステムで小さく試す」進め方がおすすめです。
・どのデータをどのエージェントに渡すのか
・エージェントがどの範囲の操作を行うのか
・人が必ずレビューすべきポイントはどこか
といった観点は押さえておくとよいです。これらを整理したうえで、情報システム部門やセキュリティ担当と対話すると議論が進みやすくなります。
例えば、社内ドキュメントの要約や戦略立案にはGeminiを使い、ブラウザベースの定型作業にはOperatorを使うなど、 業務ごとに適切な役割を割り当てることができます。
ただし、管理コストやルールの複雑さも増えるため、最初はどちらか一方を中心に試し、徐々に広げるアプローチが安心です。
・重要なアウトプットには必ず人がレビューするフローを設ける
・エージェントが参照できるデータや権限を、必要な範囲に抑える
・NG例や注意点を明文化したガイドラインをチームで共有する
といった工夫が有効です。
最初は「AIの提案をもとに人が意思決定する」形から始めると、比較的安心して運用できます。
・自社の業務に関わりそうなトピック(例:エージェント、ワークフロー、マーケ向け機能)に絞る
・月に一度程度、「今月のAIトピック共有会」を社内で開き、気になるニュースを持ち寄る
・ベンダーやパートナー企業のブログ・イベントを情報源として活用する
といった方法で、無理のない範囲でキャッチアップするのがおすすめです。
特に、レポート作成や資料整理などの時間がかかるタスクが多い場合は、 小さなパイロットからでもエージェント活用を試す価値があります。
まずはフル導入を目指すのではなく、
「週に1時間分でも業務を軽くできないか?」という視点で検討してみるとよいでしょう。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。












-7-320x180.png)






-99-120x68.png)