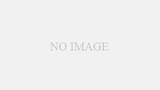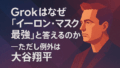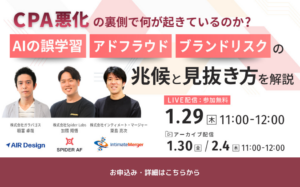Google、「Nano Banana Pro」で画像生成AIを本格プロユースへ
2025年11月、Googleは新しい画像生成モデル**「Nano Banana Pro」**を発表しました。これは既存モデル「Nano Banana」の上位版で、Gemini 3をベースにした最新世代の画像生成AIです。
従来モデルと比べて、
-
高度な編集機能
-
2K/4Kまでの高解像度生成
-
正確なテキスト(文字)の描画
-
Web検索と連携した最新情報ベースの生成
といった点が大きく強化されています。
単なる「きれいな画像を作るAI」から、プロフェッショナルがコントロールできる“制作パートナー”に進化したのがNano Banana Proの位置づけと言えます。
Nano Banana Proの概要:Gemini 3ベースの画像生成モデル
Nano Banana Proは、Googleが同じ週に発表した大規模言語モデル「Gemini 3」上に構築された画像生成モデルです。
-
前モデル:Nano Banana
-
軽量で安価な画像生成/簡易編集が得意
-
-
新モデル:Nano Banana Pro
-
画質・編集自由度・テキスト表現・Web連携などを大幅に強化した“Pro版”
-
Googleは、Nano Banana Proをクリエイターやプロフェッショナル向けと位置づけており、より細かな表現コントロールと高品質な成果物を求めるユースケースにフォーカスしています。
4つの大きな進化ポイント
LPの内容から、Nano Banana Proの進化ポイントは大きく次の4つに整理できます。
編集機能の強化:カメラ・光・色を細かく指示できる
Googleは、Nano Banana Proを「プロにより高いコントロール性を提供するモデル」として紹介しています。
具体的には、プロンプト側から次のような指定が可能になります。
-
カメラアングル(俯瞰/ローアングルなど)
-
シーンのライティング(朝焼け風・スタジオライティングなど)
-
被写界深度・ボケ具合
-
ピント位置・フォーカス
-
カラ―グレーディング(シネマティック/ヴィンテージ調など)
前モデルでもスタイル指定はできましたが、Proでは写真・映像制作に近いパラメータを細かくコントロールできるレベルに拡張されています。
マーケター目線では
「同じ構図で、トーンだけ変えたバリエーションを量産する」
「ブランドガイドラインに沿った色味・光の雰囲気を統一する」
といったニーズにハマりやすい進化です。
解像度の大幅強化:最大4Kまで対応
前モデルのNano Bananaは、最大 1024×1024px の画像生成が上限でした。
Nano Banana Proでは、
-
2K(1080p相当)
-
4Kクラスの高解像度
で画像を生成できるようになっています。
これにより、以下のようなユースケースでも“AI生成画像をそのまま本番で使いやすくなる”のが大きなポイントです。
-
LPやコーポレートサイトのメインビジュアル
-
大型ディスプレイ広告・DOOHのクリエイティブ草案
-
4K動画用の背景イメージやカット素材
-
高精細なパンフレット・ポスター用ビジュアル
従来は「AIでベースを作り → デザイナーが描き直す」という流れだったケースも、Pro品質なら補正だけで済む場面が増えることが期待できます。
テキスト(文字)表現の精度向上
画像生成AIの「あるある課題」が文字の崩れ/意味不明な単語でした。
Nano Banana Proでは、文字のレンダリング精度が大きく改善され、多様なフォント・スタイル・言語に対応できるとされています。
LPでは、Nano Banana Proが、
-
より正確なテキスト描画
-
異なるフォント・スタイル・言語でのテキスト生成
に対応することが明記されています。
マーケティングの現場でいえば、次のようなクリエイティブ制作が現実的になります。
-
OGP画像:タイトルテキストを含んだSNSシェア画像
-
バナー広告:キャッチコピーを含んだ静止画バナー
-
イベント告知用サムネイル:日付・会場名入りのキービジュアル
-
店頭POPやポスターのデザイン案
「文字は後からデザイナーがPhotoshopで載せる前提」から、
“AIが文字まで含めて一旦案を作る → 人間が微修正”というワークフローへの移行が進みそうです。
Web検索と連携:最新情報を反映した画像生成
今回の発表で特にユニークなのが、Web検索機能との統合です。
LPでは、たとえば
-
レシピをWebで検索し、その内容をもとにフラッシュカード風の画像を生成する
といった使い方が紹介されています。
これは、単に「テキストと画像を作るAI」から、
-
外部の最新情報を取りに行く
-
その情報をもとに構造化されたビジュアル(インフォグラフィック等)を作る
という動きに踏み込んだことを意味します。
マーケター的には、
-
「最新のトレンド」「直近の統計情報」「新製品の仕様」などを反映した
インフォグラフィックや説明図をAIに任せられる -
コンテンツ企画 → 情報リサーチ → 図版ラフ作成の一連の流れが半自動化される
といったインパクトが想像できます。
料金:高品質化と引き換えにコストは上昇
Nano Banana Proは、高品質化の代わりに生成コストが上がっている点にも触れられています。
LPによると:
-
旧Nano Banana
-
$0.039 / 1024px画像 1枚
-
-
Nano Banana Pro
-
$0.139 / 1080p or 2K画像 1枚
-
$0.24 / 4K画像 1枚
-
となっており、1枚あたりのコストは数倍になっています。
一方で、高解像度&編集機能付きであることを踏まえると、
-
カメラ撮影+スタジオ費+レタッチ工数
-
外注先への依頼コスト+フィードバックのやり取り
と比較した場合、1枚あたり数十セントで高品質な試作案を何十枚も出せるのは、依然として非常に強力なオプションです。
企業としては、
-
「最初のコンセプト案・たたき台」用として大量生成
-
絞り込んだ数案だけを4Kで高品質生成して仕上げ
といった段階的な使い分けをすると、コスト効率がよくなります。
どこで使える?:GeminiアプリからWorkspace、APIまで
Nano Banana Proは、Googleのさまざまなプロダクトに段階的に組み込まれます。
LPによると:
-
Geminiアプリ
-
デフォルトでNano Banana Proを利用
-
無料プランでは利用回数に上限があり、超過後は従来のNano Bananaに切り替え
-
-
Gemini AI Plus / Pro / Ultra(有料層)
-
より高い画像生成上限
-
NotebookLMでの利用にも対応
-
-
検索(Search)のAIモード
-
AI Pro / Ultraユーザー向けに、検索体験の中でNano Banana Proを利用可能
-
-
Flow(動画制作ツール)
-
Ultraプランユーザーは、動画用のビジュアル生成にNano Banana Proを利用可能
-
-
Google Workspace(Slides / Vidsなど)
-
プレゼン資料・動画用スライド内での画像生成に対応
-
-
開発者向け
-
Gemini API
-
Google AI Studio
-
新しいIDE「Antigravity」からも利用可能
-
このラインアップを見ると、GoogleはNano Banana Proを
「個人ユーザーのアイデアスケッチ」から
「企業の資料・動画制作」
「開発者が組み込むB2Bサービス」
まで、横断的な“画像生成レイヤー”として展開しようとしていることがわかります。
マーケター視点の具体的な活用シーン
ここからは、B2B/B2C問わずマーケティング担当者がイメージしやすい活用例を整理します。
広告クリエイティブ制作(バナー/LPビジュアル)
-
キャンペーンバナーの方向性を一気に10〜20案出す
-
メインビジュアルを4Kで作成し、LP/記事のアイキャッチに活用
-
ライティングやカメラアングルを変えたA/Bテスト用クリエイティブを量産
Nano Banana Proの高解像度・編集機能を前提にすると、
「カンプ → 本番制作」までの手戻りを減らす効果が期待できます。
ソーシャルメディア用サムネイル・OGP画像
-
YouTube、X、Instagramなどのサムネイル画像
-
記事シェア用のOGP画像に、テキスト入りで一発生成
テキストレンダリング精度の向上により、
「タイトル・サブコピー・日付」までを含んだサムネ案をAIが出し、
人間がフォントや余白を微調整するだけ、という運用に近づきます。
ホワイトペーパー/レポートの図解・インフォグラフィック
Web検索×画像生成を使って、
-
最新統計を反映したインフォグラフィックのタタキを作る
-
「トレンドの要点3つ」を図解したスライドイメージを作る
といった使い方がイメージできます。
NotebookLMやSlidesとの連携により、
文章コンテンツ(レポート原稿)
→ 要約
→ 図解案をNano Banana Proで生成
→ そのままGoogleスライドに差し込み
というドキュメント〜スライド変換ワークフローにも接続しやすくなります。
顧客ごとのパーソナライズド・ビジュアル
高精度な編集機能を活用すれば、
-
「同じ構図で、業界ごとの差分だけ変える」
-
SaaS向け/小売向け/金融向け…など
-
-
キャンペーンタイトルだけを変えた大量の派生クリエイティブ
を効率よく生成できます。
特にアカウントベースドマーケティング(ABM)や、
業界別LPを多数運用する企業にとっては、
「1toFewレベルのパーソナライズ画像」を量産する土台になり得ます。
ガバナンスと安全性:SynthIDとC2PA対応
Googleは、Nano Banana Proのローンチと並行して、
生成画像の透かし(ウォーターマーク)と検知機能の強化も打ち出しています。
LPでは、
-
SynthID(GoogleのAI生成画像向けウォーターマーク技術)を
Geminiアプリに統合 -
ユーザーが画像をアップロードすると、
その画像がGoogleの画像モデルによって生成・編集されたかを判別可能 -
将来的に、C2PAのコンテンツクレデンシャルにも対応予定
であることが示されています。
マーケター・企業側で意識すべきポイントは、
-
自社が「AI生成コンテンツをどこまで許容するか」のポリシー設計
-
SynthIDやC2PA対応を前提にした透かし入りクリエイティブ運用
-
誤情報やディープフェイクにつながる表現を避けるための
プロンプトガイドラインとレビュー体制
といった、ブランドセーフティ・コンテンツ信頼性のルール整備です。
企業が導入するときのステップと注意点
最後に、Nano Banana Proクラスの画像生成AIを
マーケティングチームで本格利用する際のポイントを整理しておきます。
小さく試す:1〜2プロジェクトでPoC
-
まずは1つのプロダクトライン/キャンペーンに限定して試す
-
「どの工程に効くか?」を検証
-
アイデア出し
-
カンプ制作
-
本番クリエイティブの一部
-
-
成果指標(工数削減・スピード・CVRなど)を決めておく
プロンプトとテンプレートの標準化
-
ブランドトーンや禁止表現を含めたプロンプトテンプレートを整備
-
「バナー用」「LPヒーロー用」「レポート図版用」など用途別に
テンプレを作り、再利用性を高める -
Nano Banana Proのカメラ・光・色指定のプリセットも共有しておく
コスト管理ルール
-
4K生成は「最終候補案のみ」など、解像度とコストのルールを設ける
-
生成ログや請求を定期的にレビューし、
-
ムダな試行回数が多いチーム
-
品質に対して過剰な解像度を使っているケース
などを可視化・改善
-
コンテンツレビューとコンプライアンス
-
AI生成画像は必ず人間の最終チェックを通すルールを徹底
-
ストック素材や他社IPとの類似性に注意しつつ、
社内法務やブランドチームと連携 -
SynthID/C2PAを活用し、
「AI生成であることの透明性」を担保する方向性も検討
まとめ:Nano Banana Proは「プロの現場を前提にした画像生成AI」
改めて、Nano Banana Proのポイントを整理すると:
-
Gemini 3ベースの最新画像生成モデル
-
カメラアングル・光・色などを細かく制御できる高度な編集機能
-
2K/4K対応の高解像度生成
-
フォント・スタイル・多言語に対応した精度の高いテキスト描画
-
Web検索との連携による最新情報ベースのビジュアル生成
-
Geminiアプリ/検索AIモード/Workspace/APIなど
Googleのエコシステム全体への展開 -
SynthID・C2PA対応による透明性とガバナンスの強化
という構図になります。
マーケティングの現場では、
「とりあえず画像を出してくれるAI」
から
「ブランドとKPIを踏まえて、
制作プロセスそのものをアップデートしてくれるパートナー」
として、Nano Banana Proのようなモデルとどう付き合っていくか、
2026年以降の重要なテーマになっていきそうです。
参考サイト
TechCrunch「Google releases Nano Banana Pro, its latest image-generation model」

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。

















-7-320x180.png)