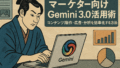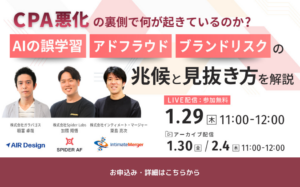ついに登場した最新モデル「Gemini 3」。マーケティング担当者が知っておきたい特徴・料金体系・具体的な利用シーンと、今日から安全に試すためのステップを、図解イメージを意識しながら丁寧に整理します。
※ 本記事の内容は公開情報をもとにした一般的な解説です。機能や料金の詳細は公式サイトで最新情報をご確認ください。
生成AIを巡る環境はここ数年で大きく変わりました。そんな中で登場した「Gemini 3」は、GoogleがこれまでのGeminiシリーズで培ってきた マルチモーダル(テキスト・画像・音声・動画などをまとめて扱う)と推論能力をさらに強化した新モデルです。
マーケティング担当者の視点で見ると、Gemini 3は「アイデア出し」「コンテンツ制作」「レポート作成」「カスタマーサポート」まで、一連の業務を支える パートナーとして活用しやすい設計になっています。特に、Google Workspace や Android、開発者向けの Vertex AI / Gemini API など、 既存のGoogleプロダクトと密接に連携している点は、日常のワークフローに乗せやすいポイントです。
本記事では、Gemini 3をまだ触っていない、あるいは軽く試しただけというマーケティング担当者の方に向けて、 「仕組み」「料金体系」「活用シーン」「導入ステップ」を、図解イメージを想像しやすい形で整理します。
📚概要
Gemini 3は何者で、どこからどう触れるのか。
Gemini 3とは?やさしく整理
Gemini 3は、Googleが提供する最新世代のAIモデルです。テキストだけでなく、画像・音声・動画をあわせて理解し、 企画書の作成からコード生成までさまざまなタスクを支援できる、汎用性の高いモデルとして設計されています。
これまでのGemini 2.x系と比べて、より複雑な指示の理解や、複数ファイルをまたぐ情報整理、 ツール呼び出しを伴う「エージェント的」な動きが得意になっており、マーケティングの現場でも 「一緒に考えてもらう」感覚で使えるようになってきています。
推論・マルチモーダル・エージェント性
単なる文章生成だけでなく、条件の整理・仮説の比較・長い資料の要約や複数媒体の横断的な理解が得意です。 画像や動画も入力として扱えるため、クリエイティブやレポートとの相性も良い設計になっています。
アプリからAPIまで幅広く提供
一般利用者向けのGeminiアプリ、Google Workspace(Gmail / Docs / Sheets など)、 開発者向けの Google AI Studio / Vertex AI / Gemini API など、多層的に提供されています。
主なアクセス方法と使い分けイメージ
日常のチャット・下書き用途に
企画の壁打ち、メールの下書き、アイデア出しなど、個人の「思考の相棒」として気軽に利用。 スマホやブラウザからアクセスできるため、まずはここから試すケースが多いです。
既存ドキュメントを生かした活用
Gmail / Docs / Sheets / Slides / Vids などに組み込まれた「Gemini in Workspace」を使うと、 既存の資料やメールをベースにした自動要約・草案作成・整理が行いやすくなります。
自社プロダクト・業務ツールへの組み込み
Google AI Studioでプロトタイプを作成し、その後 Vertex AI や Gemini API を通じて 自社のダッシュボードやマーケツールと連携させる、という流れが企業利用では一般的です。
料金体系のざっくりイメージ
Gemini 3まわりの料金体系は日々アップデートされていますが、大きく分けて次のようなレイヤー構造で提供されています。
- 無料利用枠:Web版のGeminiやAI Studioで、軽めの検証や学習に使える範囲。
- 個人向けサブスクリプション:Google AI Pro / Ultra などのプランで、Gemini 3 Pro への優先アクセスや、Workspace連携の上限拡張などが含まれる構成。
- 開発者・企業向けAPI課金:Gemini API / Vertex AI で、トークン(入力・出力の文字数やデータ量)ベースの従量課金モデルが用意されています。
マーケティング担当者として料金を確認するときは、「個人で試す」「チームでWorkspace中心に使う」「自社サービスに組み込む」のどこまでを想定するかを先に決めてから、 それぞれに対応するプランを見比べると整理しやすくなります。
🎯利点
マーケティング担当者にとっての「Gemini 3らしさ」。
マーケティング視点で押さえたい主なメリット
Gemini 3は、単に「文章生成が速いモデル」というより、マーケ施策全体の思考プロセスを支えてくれる相棒として設計されています。 ここでは、日々の業務に直結しやすい利点を整理します。
- 複数チャネルの素材を横断して整理できる(Web・SNS・動画など)
- ペルソナやカスタマージャーニーを踏まえた提案がしやすい
- チームで使う前提のワークフロー設計がしやすい(Workspace / API連携)
- ガバナンスや安全性に配慮した設計が進んでいる
長い文脈や複雑な条件の整理が得意
キャンペーン概要、過去レポート、ペルソナ定義、KPI設定資料など、複数のドキュメントをインプットしてもらい、 「要点の整理」「矛盾の指摘」「案の比較」といった処理を任せやすくなりました。
テキストとクリエイティブの両面をサポート
テキスト生成に加え、画像生成モデルやマルチモーダル入力を活用することで、 バナー・動画・LPの構成案など、ビジュアル施策との連携も取りやすくなっています。
Google製品との連携で「いつもの仕事」に溶け込みやすい
すでに多くの企業が使っている Gmail / Docs / Sheets / Slides / Android Studio などにGemini 3が統合されており、 新しいツールを増やさずにワークフローへ取り入れやすい点は、現場の負担を抑えるうえで大きな利点です。
エンタープライズ利用を意識した設計
Vertex AI や Gemini API では、大規模利用を想定した権限管理や監査機能、ログ管理の仕組みが整えられており、 企業の規模が大きくなっても運用しやすい構成になっています。
すべてをAIに任せるのではなく、「思考の整理」「たたき台の生成」「案の比較」といった工程にGemini 3を組み込み、 最終判断やクリエイティブの細部は人が握る、という役割分担を意識することがポイントです。
💡応用方法
「具体的にどんな仕事を任せられるか?」を図解イメージで整理。
日々のマーケ業務を「マインドマップ的」に支援
ここでは、マーケティング担当者が実際の現場でGemini 3をどう使えるかを、グラレコ風のイメージで分解してみます。
企画・戦略フェーズでの活用
- 過去のキャンペーン資料やレポートを読み込ませて、成功・失敗パターンを整理してもらう。
- ターゲット像や提供価値を入力し、ペルソナとカスタマージャーニーのたたき台を作成してもらう。
- 競合の打ち手やトレンド情報を要約させ、自社ならではのポジショニング案を複数提示してもらう。
「以下の資料を読んで、ターゲット像・訴求軸・KPIを整理し、3パターンのキャンペーンコンセプト案を出してください。 それぞれ、想定チャネル(検索・SNS・動画など)と、期待されるユーザー行動もメモしてください。」
コンテンツ制作フェーズでの活用
複数チャネルのコピー案を一括生成
1つのメインメッセージから、検索広告、SNS広告、ディスプレイ広告、動画スクリプト用のコピーを一度に生成し、 チャネル横断でトーンをそろえつつ、媒体特性に合わせた言い回しに調整してもらうことができます。
構成案のたたき台づくり
読者ペルソナと訴求ポイントを与えて、アウトライン・見出し案・CTA案をまずGemini 3に作ってもらい、 そのうえで自社のナレッジや事例を肉付けしていく使い方がしやすくなります。
分析・レポートフェーズでの活用
- Google Analytics や広告管理画面からエクスポートしたCSVの要約案をつくる。
- 週次・月次レポートの「構成テンプレート」をGemini 3に作ってもらい、毎回の更新作業を効率化する。
- 複数媒体の数字をまとめたスプレッドシートをもとに、施策ごとのハイライト・改善アイデアを箇条書きで提案してもらう。
「添付したスプレッドシートをもとに、今月の主要KPIの変化と要因を3つに整理し、 マーケティング部長向けの報告用サマリー(300〜500文字)を作成してください。専門用語は最小限にし、読み手のアクションがイメージしやすい表現にしてください。」
社内コミュニケーション・教育での活用
- 新人向けに、自社のマーケ施策の歴史やルールを教える簡易教材を作る。
- 経営層向けに、マーケティング施策の背景や意図をわかりやすく整理した説明資料を作る。
- 複数の議事録をまとめて読み込ませ、共通して議論されている論点を抽出してもらう。
🚀導入方法
「まずは個人で」「次にチームで」の二段階で考える。
ステップゼロ:社内ルールを確認する
企業によっては、すでに生成AIの利用ポリシーやツール選定方針が定められているケースもあります。 Gemini 3を本格的に使う前に、利用可否・利用範囲・データ取り扱い方針を必ず確認しておきましょう。
個人で試すときの導入ステップ
- GoogleアカウントでGeminiにアクセスする
まずはブラウザやモバイルアプリからGeminiにログインし、無料で利用できる範囲で基本的な動きを試します。 - 「日々の仕事1つ」を決めて使ってみる
例:週次レポートのドラフト作成、メールのテンプレート作り、SNS投稿案の下書きなど。 - 良かった活用例と注意点をメモしておく
「ここまでは役に立つ」「ここから先は自分で判断したい」といったラインを自分なりに言語化しておくと、 チームに展開するときに説明しやすくなります。
チームで導入するときのステップ
利用シーンの優先順位を決める
すべての業務にいきなり広げるのではなく、「効果が出やすく、リスクが低い範囲」から始めるのがおすすめです。 例:記事やレポートの下書き、広告コピー案の作成など。
プロンプトのテンプレート化
実際にうまくいったプロンプトをテンプレートとして整理し、Notionやドキュメントに共有することで、 チーム全体の学習スピードを高めることができます。
小規模なPoC(検証)を行う
一部チーム・一部案件でGemini 3を使った業務フローを試し、 作業時間の削減度合いやアウトプットの質、レビュー工数の変化などを観察します。
Workspace・API連携による本格導入
検証で手応えがあれば、Google AI Pro / Ultra プランや Workspace / Vertex AI / Gemini API などを組み合わせ、 社内ツールと連携した本格運用を設計していきます。
- 社内外の機密情報の取り扱いルールを明確にし、学習に使う情報の範囲を決める。
- AIの出力内容を鵜呑みにせず、事実確認やレビューのプロセスを残す。
- 利用ログやプロンプトの共有方法を整え、属人化を避ける。
🔮未来展望
「チャット」から「インターフェースそのもの」へ。
Generative UIとエージェントの時代へ
Gemini 3に関する発表では、テキストチャットだけでなく、Generative UI(生成UI)や エージェント的なコード生成といった方向性が強調されています。
- Generative UI:ユーザーの要望に応じてUIパーツを自動で組み立てる仕組み。
- エージェント:単発の回答ではなく、複数のステップを自律的に進めてくれるAIの形。
マーケティングの世界では、これが「ダッシュボードの自動構築」「シナリオに応じたフォーム生成」「一時的なキャンペーン専用UIの自動生成」といった形で現れてくる可能性があります。
マーケ組織側の準備として考えておきたいこと
- データ資産を整理する:レポート・企画書・クリエイティブなどのデータを扱いやすい形に整理しておくことで、Gemini 3を通じた再活用がしやすくなります。
- プロンプトの「型」をチーム内で共有する:社内用語やブランドトーンを含んだプロンプトテンプレートを用意しておくと、出力のばらつきを抑えられます。
- 人が判断すべきポイントを明確にする:予算配分・ブランドリスク・最終承認など、人が判断するべき領域を言語化しておくと、AI活用が組織に馴染みやすくなります。
📌まとめ
「まず1つの業務から」はじめ、少しずつ範囲を広げていく。
Gemini 3は、Googleが提供する最新世代のAIモデルとして、推論力・マルチモーダル対応・エージェント的な動きを強化しています。 マーケティングの現場では、
- 企画・戦略フェーズでの「思考の整理・壁打ち」
- コピー・記事・LP・動画スクリプトなどの「コンテンツ制作のたたき台生成」
- レポートやログの「要約・論点整理・改善案の提案」
- 社内教育や経営層向け説明資料の「わかりやすい構成づくり」
といった形で、すでに多くの活用余地があります。
重要なのは、いきなりすべてを変えようとしないことです。 「週次レポート」「広告コピー案」「社内資料の整理」など、既存業務の一部をGemini 3に任せてみるところからスタートし、 効果や課題を観察しながら少しずつ範囲を広げていくと、現場にストレスをかけずに導入しやすくなります。
本記事をきっかけに、まずはGeminiアプリやAI Studioで軽く触ってみて、 「自分の業務だと、どの部分と相性が良さそうか?」をイメージしていただければ幸いです。
❓FAQ
Gemini 3について、マーケ担当者がよく気にするポイント。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。




-7-320x180.png)