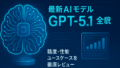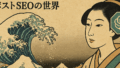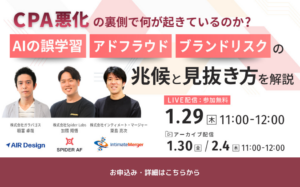ChatGPTに“推される”サイトになるには?AIを攻略するLLMO戦略の実践ポイント
ChatGPTや各種AIアシスタントが「情報の玄関口」になりつつある今、検索結果の順位だけを見ていると、ユーザーとの接点を取りこぼす可能性があります。本記事では、ChatGPTなどの生成AIから“推される”サイトを目指すために、マーケティング担当者が押さえておきたいLLMO戦略の考え方と実践ポイントを整理します。
ChatGPTはリンク一覧を並べるのではなく、答えを組み立ててから、参考情報としてサイトを紹介します。ここに、従来のSEOとは少し違う発想が必要になります。
イントロダクション
もはや「とりあえずググる」だけではなく、「とりあえずChatGPTに聞いてみる」という行動が一般化しつつあります。検索キーワードではなく、自分の状況や悩みをそのまま文章で投げる人も増えています。
そのとき、ChatGPTはさまざまな情報源をもとに回答を構成し、必要に応じて「参考リンク」や「検討候補」を挙げます。マーケティングの視点から見ると、これはこう言い換えられます。
- 従来:検索結果ページ(SERP)の中で、自社サイトがクリックされるかどうか
- これから:ChatGPTの回答の中で、自社サイトやブランドが紹介されるかどうか
入口が検索エンジンだけではなく、「AIアシスタント」にも広がっている、というのが現在の状況です。
この変化に対応するキーワードが、LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)です。本記事では、とくにChatGPTを意識しながら、
- ChatGPTに“推される”サイトの特徴
- LLMO戦略とSEOの関係
- 今日から実践できるチェックポイント
を、マーケティング担当者視点で整理していきます。
概要:ChatGPTとLLMO戦略の基本理解
ChatGPTに“推される”とはどういう状態か
まず、「ChatGPTに推されるサイト」とは、何を指しているのでしょうか。イメージしやすいように、いくつかのパターンに分解してみます。
- ChatGPTが回答の中で、ブランド名やサービス名に言及してくれる
- 「おすすめ」「比較」などの質問に対し、候補のひとつとして名前が挙がる
- 「詳しく知りたい場合は◯◯のサイトを参照して」といった形でサイトURLが紹介される
- 自社サイトに書いた考え方やフレームワークが、回答の中で要約・引用される
もちろん、ChatGPTの内部アルゴリズムを直接コントロールすることはできませんが、「AIにとっても、人にとっても読みやすいコンテンツ」を増やすことで、こうした状況に近づいていくことはできます。
LLMO戦略とは何か
LLMOとは、Large Language Model Optimizationの略で、ChatGPTのような大規模言語モデルが情報を理解・引用しやすいように、自社サイトやコンテンツを整える考え方です。
- 検索エンジンの結果ページで、特定キーワードの順位を上げる
- タイトル・メタディスクリプション・内部リンクなどの調整
- クリック率・セッション数・コンバージョンなどを主な指標とする
- ChatGPTなどのAIが、回答を作る際にどう情報を解釈するか
- AIが引用したくなる「定義」「フレームワーク」「Q&A」の設計
- ブランド名・サービス名などの一貫した表現と文脈づくり
- SEOとLLMOはどちらか一方を選ぶ話ではなく、役割の違う「セット」
- 良いSEOの土台(情報の整理・構造化・ユーザー目線)は、そのままLLMOにもプラス
- LLMOは「AIから見た自社サイト」を意識した追加のレイヤーと考えるとわかりやすい
「検索エンジンからどう見えるか」に加えて、「ChatGPTなどのAIからどう見えるか」をセットで考えることが、これからのWeb戦略の前提になりつつあります。
利点:ChatGPT目線でのLLMO戦略がもたらす効果
ChatGPTを意識したLLMO戦略に取り組むメリットは、「AIに名前を挙げてもらう可能性が高まる」ことだけではありません。コンテンツマーケティング全体の質を整える効果も期待できます。
検討初期の情報収集フェーズで想起されやすくなる
ChatGPTは、「◯◯の始め方」「◯◯の選び方」「◯◯業界の主要なプレーヤー」といった、まだ具体的な比較候補が決まっていない段階の質問と相性が良いです。
- セミナーや広告だけでは届きにくい、初期検討のユーザーとの接点が増える
- 「業界の代表的なプレーヤーのひとつ」として認識されるきっかけになる
- まだブランドを知らない層にとっても、自然な形で名前が目に入る
コンテンツの構造化が進み、社内外で再利用しやすくなる
ChatGPTにとって扱いやすいコンテンツは、人間にとっても整理されたナレッジであることが多いです。Q&Aやチェックリスト、ステップ解説などを意識することで、
- 営業資料や提案書への転用がしやすくなる
- カスタマーサポートの応対スクリプトや社内FAQに流用しやすくなる
- 社内向けAIアシスタントの学習データとしても活用しやすい
ブランドの「語られ方」を整理するきっかけになる
ChatGPTは、単一の記事だけでなく、複数の情報源を統合して回答を生成します。そのため、ブランドやサービスの語られ方に一貫性がないと、意図しない印象でまとめられる可能性があります。
- ブランド名・サービス名・略称の表記ゆれを見直す必要が出てくる
- 「自社は何を得意としているのか」を明文化するきっかけになる
- コアメッセージを軸に、コンテンツの方向性を整理しやすくなる
「SEO指標だけ」に偏らない評価軸を持てる
従来のレポートは、どうしてもセッション数・順位・CV数といったSEO寄りの指標に偏りがちでした。LLMO視点を取り入れることで、
- ChatGPTでブランドやテーマを尋ねたときの回答内容の変化
- ChatGPTが挙げる競合・比較候補の顔ぶれの変化
- 問い合わせ・商談で「AIで調べていた」という声が出てくるかどうか
など、「どう語られ、どう選ばれているか」という観点を持ちやすくなります。
応用方法:ChatGPTに“推される”ためのコンテンツ設計
ここからは、ChatGPTを意識した具体的なコンテンツ設計のポイントを、グラフィックレコーディング風のイメージで整理していきます。
質問ベースで記事構造を組み立てる
ChatGPTは「質問」に答える存在です。そのため、「どんな質問に答える記事か」をはっきりさせると、AIとの相性が良くなります。
企画の段階で「Q&Aメモ」を作っておくと、本文を執筆するときにも、AIにとっての読みやすさを意識しやすくなります。
エンティティページで「公式な説明」を用意する
ChatGPTは、企業名やサービス名といった「エンティティ」を理解しながら回答を組み立てます。そのため、自社のブランド・サービスについて、公式な説明が集約されているページを用意しておくことが重要です。
- サービスの一文説明(タグラインではなく、説明文)
- 提供している機能や価値の概要
- 主な利用シーン・対象ユーザー
- 代表的な導入事例や活用イメージ
- 重要なキーワードを吹き出し風の見出しで強調する
- 「◯◯ならこのサービス」という関係性を図解で表現する
- 用語の定義などは短い枠線付きボックスでまとめる
比較・選び方コンテンツはニュートラルに整理する
ChatGPTは、バランスの良い情報を好みます。自社だけを過度に持ち上げる文章よりも、選び方や向き・不向きを整理した比較コンテンツのほうが、引用されやすい土台になります。
- 自社と他社の強み・弱みを両方とも整理して記載しているか
- 「このようなケースではA社が向きやすい」といった中立的なコメントがあるか
- 価格・機能だけでなく、「サポート体制」「導入負荷」など判断軸も提示しているか
「ストーリー」と「ナレッジ」の両方を用意する
ChatGPTは、具体例やストーリーも好みますが、ナレッジとして整理された情報も必要とします。そのため、オウンドメディアでは、
- ストーリー型:事例インタビュー、プロジェクトの舞台裏など
- ナレッジ型:ノウハウ解説、チェックリスト、フレームワーク紹介
の両方をバランスよく用意しておくと、ChatGPTが回答を構成する際に、背景と結論の両方を提供できる情報源として位置付けられやすくなります。
導入方法:今日から始めるChatGPT向けLLMOチェックリスト
ここでは、マーケティング担当者が実務の中で取り組みやすいように、ChatGPTを意識したLLMO導入ステップをチェックリスト形式で整理します。
現状把握:ChatGPTに自社を質問してみる
まずは、次のような質問をChatGPTに投げて、回答をメモしてみてください。
- 「◯◯社について教えてください」(自社名)
- 「◯◯社の◯◯サービスはどのような特徴がありますか?」
- 「◯◯領域で代表的なサービス / ツールを教えてください」
そのうえで、次のポイントを簡単にチェックします。
- 自社の説明が、実際のポジショニングに近いかどうか
- 紹介されている競合の顔ぶれに違和感がないか
- 参考サイトとして、どのドメインが挙がっているか
重要ページの洗い出し:先に整える「コア」を決める
いきなり全ページを見直すのではなく、ChatGPTから見ても重要そうな「コアページ」から手を付けると効率的です。例えば、
- サービス概要ページ(エンティティページ候補)
- よく読まれている基礎解説記事
- 比較・選び方系の記事
- 代表的な事例・ユースケースの記事
コンテンツの型を揃える:LLMO対応テンプレートを決める
チームでコンテンツを制作している場合、共通テンプレートを決めて共有しておくと、LLMO視点が浸透しやすくなります。
- 冒頭:一文で結論+誰向けの記事か
- 定義:用語の意味をやさしく説明
- メリット・注意点:箇条書きで整理
- 具体的なステップ・チェックリスト
- よくある質問(Q&A形式)
- 導入:比較の前提条件・想定読者を明記
- 比較軸:2〜5個の判断基準を定義
- サービスごとの特徴を同じフォーマットで整理
- タイプ別のおすすめパターン(例:小規模〜大規模)
- 検討時に確認したいチェックリスト
構造化と技術的な土台の確認
LLMOはコンテンツ設計が中心ですが、基本的なSEOの土台も引き続き重要です。とくに、
- タイトルと見出し構造(h1〜h3)が論理的に並んでいるか
- パンくずリストやナビゲーションで文脈が伝わるか
- FAQページがある場合はQ&A形式で整理されているか
こうした点を見直すことで、「人にとってもAIにとっても読みやすい」サイトに近づきます。
定期的な振り返り:LLMOメモをレポートに追加する
毎月や四半期のレポートに、「LLMOメモ」を1ページ添えるだけでも、社内での意識が変わってきます。例えば、
- ChatGPTで自社名を聞いたときの回答のスクリーンショット
- ChatGPTに「◯◯領域の主要プレーヤー」を聞いたときのリスト
- 前回との違い・新しく挙がった競合・変化した表現のメモ
数値化しづらい部分もありますが、「どう語られているか」を定点観測することで、コンテンツ施策の方向性を調整しやすくなります。
未来展望:AIエージェント時代の「推されるサイト」とは
ChatGPTをはじめとする生成AIは、今後さらに機能が拡張され、検索だけでなく、タスク実行やエージェント的な動きも担うようになると考えられています。そのとき、「推されるサイト」の意味合いはもう少し広がります。
AIエージェントが「動く」ためのナレッジとして選ばれる
たとえば、次のような状況が現実味を帯びてきています。
- 「自社に合うマーケティングツールを3つ比較してレポートにまとめて」とAIに依頼する
- AIが複数のサイトを参照し、機能・価格・向き・不向きを整理してくれる
- そのレポートの参考資料として、特定のオウンドメディアが挙げられる
このとき、AIが「比較に使いやすい」と感じる情報をどれだけ提供できているかが、推されるかどうかに影響してきます。
「SEOの終わり」ではなく、「入口の多様化」への対応
SEOはこれからも重要ですが、入口が増えることで役割が分かれていきます。
- 検索エンジン:自分からキーワードを打ち込むユーザーの入口
- ChatGPTなどのAI:相談ベースで情報を

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。
















-7-320x180.png)



-2025-06-24T184743.543-120x68.png)