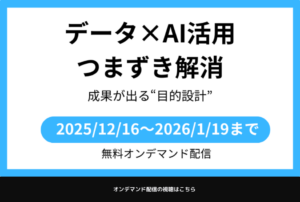ターゲティングや計測の前提が揺らぐなかで、アドテク業界は再び「コンテキスト」に注目し始めています。 その文脈で登場したのが、AIエージェント時代の新しい共通仕様として提案されている Ad Context Protocol(AdCP)です。
👋イントロダクション
プログラマティック広告が普及して以降、配信ロジックは人間がルールを設定し、 システムが自動で入札・配信を行うスタイルが主流でした。 しかし、生成AIとエージェント技術の進展により、「AIが自律的にメディアを選び、買い付ける」という 新しいパラダイムが現実味を帯びています。
その一方で、個人単位・ID単位に依存したターゲティングにはさまざまな制約がかかり、 「どのコンテキスト(文脈)に広告を出すのか」という観点が再評価されています。 こうした背景の中で、コンテキスト情報を軸にAIエージェントと広告プラットフォームをつなぐ共通レイヤーとして 注目されているのが Ad Context Protocol(AdCP)です。
「コンテキスト回帰」と「AIエージェントの普及」という、いかにも別のトレンドに見える2つの流れは、 実はAdCPを通じて一本の線でつながり始めていると言えます。
この記事は、技術仕様の細部というよりも、アドテクの構造変化を俯瞰しながら、 マーケターが今押さえるべきアクションにフォーカスしていきます。
- ✅アドテク業界が「コンテキスト」に再び注目する理由
- ✅Ad Context Protocol(AdCP)の概要と、既存標準との違い
- ✅マーケターが今日から検討できる応用方法・導入ステップ
🌐概要
アドテクが再び「コンテキスト」に注目する背景
デジタル広告の初期は、メディアのカテゴリーやページ内容など、 コンテンツの文脈に基づく配信が主流でした。 その後、ユーザー行動データや識別子を活用したターゲティングが一気に広まりましたが、 規制やプラットフォームポリシーの強化により、利用できるシグナルには多くの制約がかかるようになりました。
こうした流れの中で、「文脈」そのものを丁寧にモデリングし、 そのコンテキストとクリエイティブ・オファーをマッチングするアプローチが改めて注目されています。 生成AIの発展によって、ページの意味解析やトピック分類、トーン・意図の把握といった処理が高度化し、 従来よりもリッチなコンテキスト情報を扱えるようになっていることも追い風です。
Ad Context Protocol(AdCP)とは何か
Ad Context Protocol(AdCP)は、AIエージェントと広告プラットフォームの間でやり取りされる 「文脈」や「広告タスク」の共通言語を定義するためのオープンスタンダードです。
公式ドキュメントや各種解説によると、AdCPは次のような特徴を持ちます。
- 🧠AIエージェントを前提にしたプロトコル
人間がUIで操作するのではなく、AIエージェント同士が広告の計画・交渉・実行を行うことを前提とした仕様設計。 - 🔌Model Context Protocol(MCP)の上に構築
LLMとツール・APIをつなぐための「Model Context Protocol」の拡張として、 広告ユースケース専用のレイヤーを定義している。 - 📡シグナル発見・メディアバイイング・クリエイティブなどを共通化
Signals Activation Protocol、Media Buy Protocol、Creative Protocolといったモジュールで、 シグナル探索から買い付け、クリエイティブ管理までの一連のワークフローを標準化する構想。 - 🤝オープンな業界連合による開発
Yahoo、PubMatic、Scope3、Optable、Swivel、Triton Digital など、複数のアドテク企業が参画する オープンソースの取り組みとして始まっている。
従来標準との関係:OpenRTBやAgentic RTB Frameworkとの違い
AdCPは、すでに普及している標準仕様を置き換えるものではなく、 レイヤーが異なる存在として位置づけられています。
- インプレッション単位の入札・応札を標準化
- DSPとSSP間のリアルタイムな取引フォーマット
- 「オークションの瞬間」を扱うトランザクション層
- AIエージェントが広告ワークフロー全体を操作するための共通インターフェース
- シグナル探索、在庫キュレーション、プランニング、買い付け実行などを含む
- 「いつ・どこに・何を・どの条件で出すか」を話し合う制御レイヤー
➡ ざっくり言えば、OpenRTBが「入札パケットの標準」だとすると、AdCPは 「AIエージェント同士が広告タスクを話すための標準」というイメージです。
さらに、IAB Tech Labが提案している Agentic RTB Framework(ARTF)は、 オークションの高速化・最適化に焦点を当てた仕様として AdCP を補完する位置づけで議論されています。
👍利点
AdCPがもたらしうる業界全体のメリット
Ad Context Protocolはまだ発展途上の標準ですが、構想レベルで整理すると、 アドテク業界にとって次のようなメリットが期待されています。
- 🧵断片化したアドスタックの「共通言語」になる
DSP、SSP、アドサーバー、測定ツールなどがそれぞれ独自APIを持つ状況では、 統合や自動化に多くの開発コストがかかります。AdCPは、AIエージェントが各システムと対話するための 共通インターフェースを提供することで、この断片化を緩和しようとしています。 - ⚙️ワークフロー自動化の標準化
「ターゲットシグナルの発見」「在庫のキュレーション」「買い付け条件の交渉」「配信後の評価」といった作業は、 これまで各社の専用UIやスクリプトに分散していました。AdCPにより、これらを AIエージェントが横断的に扱えるワークフローとして標準化しやすくなります。 - 📊コンテキストシグナルの活用を体系化
ページのカテゴリやトピックだけでなく、トーン、レイアウト、周辺コンテンツなど多次元のコンテキスト情報を シグナルとしてやり取りするための枠組みが整うことで、コンテキストベースの最適化が高度化する可能性があります。 - 🔍透明性・検証性の向上
JSON Schema など機械可読なスキーマに基づき、各タスクの入力・出力・エラー条件を定義することで、 「どのエージェントが、どの条件で、どのような判断をしたか」を追跡しやすくなります。
広告主・マーケター側から見た価値
デジタルマーケティング担当者の視点では、AdCPが普及した場合、次のようなメリットがイメージしやすいでしょう。
- マルチプラットフォーム運用のハードル低減: 複数のDSPやメディアにまたがるキャンペーン設定・レポーティングを、AIエージェントに一元的に委ねやすくなる。
- 戦略・クリエイティブへの集中: 同じようなUI操作や入札ルールのコピー&ペーストに追われる時間が減り、 コンテキスト戦略やクリエイティブの仮説検証に時間を使いやすくなる。
- 新しいコンテキストの発見: エージェントが大量の在庫と成果を横断的にスキャンし、 人間が想定していなかった「意外な勝ちパターンの文脈」を提案してくれる可能性がある。
AdCPの狙いは、単に「APIをまとめる」ことではなく、 AIエージェントがコンテキストを理解しながら広告を運用できる土台をつくることにあります。 その上で、マーケターは「どのようなコンテキストでブランドを見せたいか」をより戦略的に設計していく役割を担うイメージです。
🛠️応用方法
コンテキスト戦略 × AIエージェントの具体的なイメージ
「AdCP」と聞くと、どうしても技術寄りのイメージになりがちですが、 マーケター目線では、「コンテキスト設計」と「エージェントへの指示」をどう組み合わせるかが本質です。
- 🧱 ブランドごとの「望ましいコンテキスト」を定義する
まずは人間側で、「どんな文脈で広告が出ていてほしいか」を言語化します。 例:
・BtoB SaaSなら「課題整理・業務改善・DX・組織変革」系の解説文脈
・D2Cコスメなら「自己肯定感・セルフケア・ナチュラル志向」などポジティブなライフスタイル文脈
こうした方針を、エージェントへのプロンプトやポリシーとして渡すイメージです。 - 🧭 「避けたいコンテキスト」もあわせて整理する
ブランド毀損リスクが高い文脈や、ネガティブ感情が強いコンテンツなど、 なるべく避けたいシチュエーションも同時にリスト化しておきます。 AdCPが普及すれば、これらを機械可読なポリシーとして渡すことがしやすくなっていきます。 - 📊 コンテキスト別の成果データをエージェントにフィードバック
「どのコンテキストでCVRが高かったか」「どのトーンのページでエンゲージメントが高かったか」といった情報を、 エージェントに戻すことで、コンテキスト理解を深める学習ループを回せるようになります。
AdCP的な考え方を先取りする運用のヒント
AdCPが本格標準になる前でも、考え方だけを先取りして運用に取り入れることは可能です。
- 媒体横断で「コンテキスト分類」を共通の軸にする: 媒体ごとのカテゴリやプレースメント名をそのまま見るのではなく、 自社なりの「コンテキストタグ」を定義し、どの媒体でも同じ分類軸でレポートを見られるようにします。
- 生成AIでページコンテキストを自動要約する: ランディング面のURLリストを生成AIに渡し、「どのようなテーマ・トーンか」を簡易要約させて整理することで、 コンテキストの傾向を把握しやすくなります。
- コンテキスト別のクリエイティブバリエーションを用意する: 同じオファーでも、「課題訴求型」「成功事例型」「How-to型」など、 文脈に合わせて響きやすい切り口を複数用意しておきます。
AdCP時代のコンテキストターゲティングは、単に「カテゴリを選ぶ」ではなく、 コンテキストとクリエイティブの組み合わせを、AIと一緒に設計・検証していくプロセスになるイメージです。
🚀導入方法
現時点でマーケターができる準備
AdCPはまだ標準化の途上にあり、すぐに全てのプラットフォームで利用できるわけではありません。ただし、「来るべきエージェント運用」と「コンテキスト重視」の両方に備えるために、 今からできる準備はいくつかあります。
- 現状のコンテキスト活用レベルを棚卸しする
自社の運用において、どの程度コンテンツの文脈を意識した配信が行われているかを確認します。 ・媒体ごとのカテゴリ選択だけになっていないか ・コンテキスト別に成果を見返すレポートが用意されているか などをチェックしましょう。 - 社内で「コンテキスト戦略」の共通言語をつくる
マーケティング、営業、ブランド担当が集まり、「どんな文脈でブランドを出したいか」を議論し、 用語集や簡易ガイドラインとしてまとめておくと、エージェント化の際にも指示が出しやすくなります。 - AIツールを使った簡易エージェント運用を試してみる
すでに一部のプラットフォームやツールでは、AIがキャンペーン設定や入札戦略を提案・自動実行する機能が登場しています。 これらを小さく試し、「人間がどのレベルまで任せられるか」の感覚を掴んでおくと、AdCP文脈の議論がしやすくなります。
技術チームと連携する際のポイント
AdCPはプロトコルであり、実際の実装は開発チームが担います。 マーケターとしては、次のような観点でコミュニケーションするとスムーズです。
- 📂「どんなタスクをエージェントに任せたいか」を先に定義する
例:在庫キュレーション、日別予算配分、クリエイティブテスト設計など、 やらせたい仕事を箇条書きにして伝えることで、開発側もどのモジュールから手を付けるべきか判断しやすくなります。 - 🔐データの扱い方針を明確にする
どのデータをエージェントに見せてよいか、どのデータは別管理にするかなど、 プライバシーやコンプライアンスの観点を含めて整理しておくと、導入後の運用が安定します。 - 🧪限定的なサンドボックスから始める
いきなり全キャンペーンをエージェント化するのではなく、実験用のアカウント・予算・媒体を用意し、 影響範囲を限定した検証からスタートするのが現実的です。
将来的にAdCPを直接触らないとしても、「人間がやっていた判断を、どこまでエージェントに任せるか」という ポリシーや考え方を、今のうちからメモレベルでも共有しておくと、 実際にエージェント運用を導入する際の議論がスムーズになります。
🔮未来展望
「エージェント広告インフラ」としてのAdCPの位置付け
各種メディア・コラムでは、AdCPは「エージェント広告時代の共通インフラ」として語られています。これは、OpenRTBやPrebidがプログラマティック取引の基盤となったのと同じように、 「AIが広告運用を担う時代」の配線を整える存在として期待されている、という意味です。
さらに、LiveRampの User Context Protocol(UCP)のように、AdCPを拡張する新たなプロトコルも登場し始めています。これは、コンテキストやユーザー状態を表現するレイヤーが今後さらに細分化・高度化していく可能性を示しています。
コンテキスト回帰がもたらすマーケティングの変化
コンテキストへの回帰とエージェントの普及は、マーケティングの現場に次のような変化をもたらすと考えられます。
- 🖥️「どこに出すか」の解像度が上がる
ドメインやカテゴリ単位だけでなく、ページ内のセクションやコンポーネントレベルの文脈を考慮した出稿設計が一般的になる可能性があります。 - 🎨クリエイティブとコンテキストのペア設計
1本のクリエイティブを広く出すのではなく、コンテキストごとのテンプレートを用意し、 エージェントが「どの文脈にはどのテンプレートを使うか」を最適化する世界が見えてきます。 - 📈KPI・評価軸の再設計
短期のコンバージョンだけでなく、コンテキストの質やブランド適合度といった指標を レポーティングに組み込む必要性が高まります。
コンテキストは「配信条件の一つ」から、ブランド体験の一部として より重視されていくと考えられます。そのとき、「どんな文脈にブランドを置きたいのか」を 言語化できているマーケターほど、エージェントを味方につけやすくなるでしょう。
📝まとめ
Ad Context Protocol(AdCP)は、アドテクの歴史の中で見ればまだ新しい構想ですが、 「コンテキスト」への回帰と「AIエージェント」へのシフトという 2つの大きな潮流をつなぐ重要なピースになりつつあります。
- アドテク業界は、シグナル制約の高まりを背景に、コンテンツの文脈を重視するコンテキスト戦略へと再び注目している。
- AdCPは、AIエージェントが広告プラットフォームとやり取りするためのオープン標準として構想されており、コンテキスト情報を軸にワークフローを共通化しようとしている。
- OpenRTBなどの既存標準を置き換えるのではなく、エージェントが計画・交渉・最適化を行う制御レイヤーとして位置づけられている。
- マーケターは、コンテキスト戦略の言語化、ベンダー依存度の棚卸し、エージェント運用の小さな実験などを通じて、AdCP時代に備えることができる。
- 今後、UCPなどの拡張プロトコルや他団体のフレームワークとも連動しながら、エージェント広告インフラとしてのエコシステムが形成されていくと考えられる。
重要なのは、AdCPの仕様全てを暗記することではありません。 「コンテキスト」というレンズでブランド体験を設計し、 その設計図をAIエージェントと共有していくという方向性を持てるかどうかが、 今後のアドテク環境での優位性につながっていきます。
💬FAQ
現時点では、AdCPはオープンソースとして仕様やリファレンス実装が公開され、 一部の企業・プロジェクトで検証が始まっている段階です。多くの広告主・代理店が日常的に使うにはもう少し時間がかかると見られますが、 主要プレイヤーが参加する業界連合として開発が進んでいるため、今後の普及状況をウォッチしておく価値は十分にあります。
プロトコル仕様そのものは開発者向けの内容が多いですが、マーケターとしては 「AIエージェントが、どのようなタスクとコンテキスト情報をやり取りできるようになるのか」 を理解しておくレベルで十分です。 公式サイトのイントロダクションや、マーケター向けの解説記事を読むと、 役割のイメージは掴みやすくなります。
コンテキストターゲティングはあくまで「文脈ベースで配信先を選ぶ考え方・手法」です。 一方、AdCPはその考え方を、AIエージェントが扱いやすい形で標準化するための技術レイヤーと捉えると分かりやすいでしょう。 つまり、コンテキスト戦略をどう設計するかは人間側の仕事であり、 AdCPはそれを多くのプラットフォームで実行しやすくするための共通インフラという位置づけです。
単純なUI操作やルールのコピーなど、機械的な作業はエージェントに移っていく可能性があります。 その一方で、「どんなコンテキストでブランドをどう見せるか」「どのような指標で評価するか」といった設計や、 ステークホルダーとの調整は引き続き人間の重要な役割です。 むしろ、戦略・クリエイティブ・ガバナンスの比重が高まると考えられます。
直近では、IAB Tech Labの Agentic RTB Framework(ARTF)や、 LiveRampの User Context Protocol(UCP)など、エージェント広告を意識した標準化の動きが複数登場しています。すべてを細かく追う必要はありませんが、 「どのレイヤー(取引/ワークフロー/データ)を扱う標準なのか」という観点で整理しておくと、 ニュースが出たときにも理解しやすくなります。
まずは、社内で「コンテキスト戦略メモ」をつくってみることをおすすめします。 自社にとって望ましいコンテキスト・避けたいコンテキストを簡単に言語化し、 メディア選定やクリエイティブ企画の場で共有できるようにしておくと、 AdCPのような新しい標準が普及したときにも、そのままエージェントへの指示書として活用しやすくなります。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。















-7-320x180.png)


-2025-11-18T110337.822.png)


-2025-11-18T133029.298-120x68.png)
-2025-11-18T100421.181-120x68.png)