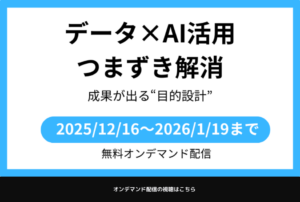AIエージェント型検索や回答エンジンが普及するなかで、公開されたウェブコンテンツを「一気にかき集めて要約し、ユーザーを原典に誘導しない」振る舞いが “スマッシュ・アンド・グラブ”と呼ばれ、議論を呼んでいます。Perplexityをはじめとするサービスをめぐる動きは、 コンテンツの作り手とマーケターにとって、無視できないテーマになりつつあります。
👋イントロダクション
ChatGPT、Perplexity、検索エンジンのAI概要表示など、ユーザーが検索結果をクリックしなくても その場で答えを得られる体験が一般化しつつあります。さらに、最近はAIエージェントが 複数サイトを自動で横断し、要約や比較、意思決定の支援まで行うようになりました。
この流れの中で、一部のテックメディアやパブリッシャーは、AIエージェントによるコンテンツ取得と提示の仕方を 「スマッシュ・アンド・グラブ(smash-and-grab)」と表現しています。 元々は「ガラスを割って店内のものを素早く奪い去る窃盗」を指す言葉ですが、 ここでは「ウェブサイトのコンテンツを一気にかき集めて、ユーザーに要約だけを見せる行為」をなぞらえた比喩です。
コンテンツを作る側からすると、「自分たちが投資して作った情報が、AIにまとめられてしまい、 トラフィックや収益につながりにくくなるのでは」という懸念が生まれます。 これはSEOやコンテンツマーケティング戦略にも直結するテーマです。
さらに、Perplexityをめぐっては、クローリングの方法やコンテンツ利用のあり方について、 パブリッシャーやインフラ企業、コミュニティから問題提起が続いています。マーケターとしては、AIエージェントをどう活用するかと同時に、 自社コンテンツをどう守り、どう共存していくかを考える必要が出てきました。
- ✅“スマッシュ・アンド・グラブ”問題の意味と背景
- ✅PerplexityをはじめとするAIエージェントのビジネスモデルとリスク
- ✅コンテンツマーケティングへの影響と、実務で取れる打ち手
🌐概要
“スマッシュ・アンド・グラブ”問題とは何か
“スマッシュ・アンド・グラブ”という言葉は、もともと物理的な窃盗の文脈で使われてきました。 ショーウィンドウを割り、商品を素早くつかんで逃げるスタイルの犯罪を指します。AIの世界でこの比喩が使われるのは、次のような振る舞いに対してです。
- 📥多数のウェブページを高速でクロールし、本文を取得する
- 🧩複数サイトの内容を組み合わせて要約・再構成する
- 📤ユーザーにはAIの回答だけを提示し、元サイトへの誘導は限定的になる
コンテンツの作り手からすると、「窓を割られて中身だけ持っていかれる」ように感じられることから、 “スマッシュ・アンド・グラブ”という表現が広まっています。
PerplexityとAIエージェント型検索の特徴
Perplexityは、いわゆる「回答エンジン」として、クエリに対してウェブ上の情報をまとめた回答を提示し、 参照元のリンクも併記するスタイルで知られています。さらに、ブラウザやアプリで動作する エージェント機能を通じて、ユーザーの代わりに複数サイトを回遊し、タスクを進める方向に進化しています。
- 検索結果としてサイト一覧を表示
- ユーザーがクリックして各サイトを閲覧
- トラフィックはサイト側に送られやすい
- AIが複数サイトを要約し、回答を生成
- ユーザーはAIの回答だけで完結しやすい
- サイトへのクリックが発生しない可能性がある
➡ 「情報への入り口」が検索結果ページからAI回答画面へと移ることで、流通の構造が変わりつつあります。
なぜマーケターにとって“重大なテーマ”なのか
デジタルマーケティング担当者にとって、AIエージェントの振る舞いは次のような点で影響します。
- オーガニックトラフィック構造の変化: 従来のSEO戦略だけでは、AI回答画面からの流入を取りこぼす可能性がある。
- コンテンツ投資とリターンのバランス: 自社で投資して作ったコンテンツに対して、どこまでAIからの利用を許容するかの判断が必要になる。
- ブランド露出の新しい形: AI回答の中でブランド名や自社コンテンツがどのように扱われるかが、認知や信頼に影響する。
「AIがコンテンツを盗んでいるかどうか」という二元論ではなく、 「AIエージェント前提の情報流通の中で、自社はどう振る舞うか」を考えることが、 マーケターにとって現実的なテーマになりつつあります。
👍利点
“スマッシュ・アンド・グラブ”議論から得られるポジティブな学び
“問題”として語られることが多いテーマですが、マーケター目線では、議論が深まることで 次のような利点もあります。
- 🧭コンテンツ戦略の再設計につながる
「AIに要約されても価値が残るコンテンツとは何か?」という問いを通じて、 企画やフォーマットを見直すきっかけになります。 - 🛡️ブランドとしてのスタンスを明確にできる
コンテンツ利用ポリシーやAIへの姿勢を公開することで、ユーザーやパートナーからの信頼を得やすくなります。 - 🤝メディア側・開発側との建設的な対話が進む
広告主、プラットフォーム、メディアが協力しながら、新しいルールやビジネスモデルを模索する土台になります。 - 📊新しいKPIや評価軸を導入するきっかけ
単純なセッション数だけでなく、AI経由でのブランド想起や指名検索など、 間接的な効果も含めた評価を検討する機会になります。
AIエージェント自体の利点も理解しておく
一方で、AIエージェントはユーザー体験の観点から多くの利点も持っています。 これを理解しておくことは、「完全に拒否する」か「無条件に受け入れる」かではなく、 うまく付き合うための前提になります。
- 情報探索の負担軽減: 複数サイトを比較する手間を減らし、概要を素早く把握できる。
- 専門外の領域へのアクセス向上: 難しいテーマも、平易な言葉でかみ砕いてくれることで、ユーザー層が広がる可能性がある。
- 音声・マルチモーダルとの組み合わせ: 音声インターフェースやスマホアプリと組み合わせることで、新しい接点が生まれる。
AIエージェントは、ユーザーにとって便利であるほど、コンテンツ側の課題も大きくなるという側面があります。 だからこそ、「どう使われたいか」をコンテンツ側から発信していくことが重要です。
🛠️応用方法
AIエージェント前提でのコンテンツ設計
“スマッシュ・アンド・グラブ”問題を踏まえつつも、AIエージェントが存在する前提で コンテンツを設計するアプローチも現実的です。マーケターが取り組みやすいポイントを整理します。
- 🧱 「表層」と「深層」の二層構造でコンテンツを設計
AIに要約されても伝わる表層情報(結論・概要)と、実際にサイトに来た人だけが得られる深層情報 (具体的なノウハウ、事例、ツール、チェックリストなど)を意識的に分けます。 - 🏷️ ブランド固有の視点やフレームワークを明示する
一般論だけだとAIに埋もれやすくなるため、自社独自のフレームワーク名や用語、図解などを使い、 「そのブランドならでは」の価値を明確にします。 - 🔗 AIから引用されてもブランドに気づいてもらえる工夫
記事内に企業名やサービス名を自然な形で繰り返し登場させることで、 AI経由で要約を読んだユーザーにもブランドが残りやすくなります。 - 🧭 「次に取るべきアクション」を明示する
記事の最後にチェックリストや診断コンテンツ、ホワイトペーパーなどの導線を置き、 AI要約だけでは得られない体験を用意します。
AIエージェント自体の活用アイデア
また、AIエージェントを「敵」としてだけ見るのではなく、 自社のマーケティングオペレーション改善に活用することも可能です。
- 競合コンテンツのラフ分析: AIエージェントに競合サイトや業界レポートの概要を整理させ、企画のインプットにする。
- 自社サイトのナレッジ整理: 自社コンテンツをもとに、よくある質問と回答の候補をAIに生成させる。
- エージェント視点での「自社の見え方」をチェック: エージェントに自社テーマで質問し、どのサイトが引用されているかを確認することで、 AI経由の「認知状況」をモニタリングする。
「AIエージェントにどう見られているか」を意識することは、 検索結果ページの順位を見るのと同じくらい、これからのマーケターにとって日常的なチェックポイントになるかもしれません。
🚀導入方法
コンテンツ利用ポリシーと技術的な対応
自社としてAIエージェントとどう向き合うかを決める際には、 ポリシー面と技術面の両方を整理しておくと、社内外とのコミュニケーションがしやすくなります。
- コンテンツ利用ポリシーの明示: 「AI学習・要約に関するスタンス」をサイト内で公開し、許容範囲や禁止事項を文章化する。
- robots.txtやメタタグによるシグナル: クローラーに対するアクセス方針を設定し、AIサービス側にシグナルを送る。
- 重要コンテンツのアクセス制御: 有料コンテンツや機微な情報については、必要に応じてアクセス制限や配信形態を検討する。
もっとも、最近の報道では、クローリング拒否設定を行っているにもかかわらず、 別の手段でアクセスしているのではないかと指摘されるケースもあり、 技術的な対策だけで完全に制御することは難しい可能性も示唆されています。
社内での検討とステークホルダー調整
マーケティング担当者が中心になって進める場合、以下のようなステップが現実的です。
- 現状把握: 自社コンテンツが、主要なAIエージェントでどの程度参照・要約されているかを確認する。
- リスクと機会の洗い出し: トラフィック減少の懸念だけでなく、ブランド露出や認知向上の機会も含めて整理する。
- 関係部門との意見交換: 法務・情報システム・編集・営業などと、ポリシーやビジネス的な観点をすり合わせる。
- 短期・中期の方針を分けて決定: すぐに実施できる対策と、中期的に検討したい施策を分けてロードマップ化する。
現実的には、コンテンツの種類やビジネスモデルごとにスタンスを分ける方が運用しやすくなります。 例えば、「ニュース速報系は制限を強めるが、ホワイトペーパーはむしろ引用を歓迎する」といったレベル感です。
🔮未来展望
訴訟・規制・業界ルールの行方
現時点でも、海外ではニュースメディアや出版社、コミュニティサービスが、 AIスタートアップに対してコンテンツ利用の在り方を問う訴訟を起こす事例が増えています。こうした動きはすぐに結論が出るものではありませんが、 「どこまでが許容される利用か」に関する指針が徐々に具体化していく可能性があります。
また、インフラ事業者が、特定のAIクローラーの振る舞いに対して問題提起し、 ボットとしての扱いを変更するケースも出てきています。これは、技術レイヤーからの「ルール形成」の一歩とも言えます。
コンテンツビジネスとAIエージェントの共存シナリオ
中長期的には、AIエージェントとコンテンツビジネスの関係は、次のようなシナリオが考えられます。
- 🤝ライセンス・パートナーシップ型
一部のメディアやデータプロバイダーとAI企業が契約を結び、 正規ライセンスに基づいて高品質データを提供するモデル。 - 🔗トラフィック共有・収益シェア型
AI回答から元コンテンツへの送客を仕組み化し、一定の収益分配を行うモデル。 - 🧱独自コミュニティ・会員制コンテンツへのシフト
オープンウェブだけに依存せず、メンバー向けの深いコンテンツやコミュニティで価値を提供するモデル。
マーケターとしては、「どのシナリオであっても機能するブランドポジション」を意識しておくと、 環境変化への耐性を高めやすくなります。
📝まとめ
AIエージェントの“スマッシュ・アンド・グラブ”問題は、単なるテクノロジー論争ではなく、 コンテンツがどう価値を生み、誰にどのように還元されるべきかという、 かなり根本的な問いを含んでいます。
- “スマッシュ・アンド・グラブ”は、AIエージェントがコンテンツをまとめて持ち去り、元サイトへの還元が弱い状態を指す比喩として使われている。
- Perplexityをはじめとする回答エンジン・AIエージェントは、ユーザーに便利な一方で、コンテンツ提供側からは懸念も持たれている。
- マーケターにとっては、AI前提のコンテンツ設計・ブランド露出・KPI設計を見直すきっかけになる。
- ポリシーと技術対応、社内外の対話を通じて、自社にとって適切なスタンスを検討することが重要。
- 今後は訴訟やガイドライン、パートナーシップモデルを通じて、コンテンツ利用のルールが徐々に具体化していくと考えられる。
デジタルマーケティング担当者としては、AIエージェントを「脅威」か「チャンス」かで単純に判断するよりも、 環境変化を前提に、自社のコンテンツとブランドの価値をどう位置づけるかを考えることが、 長期的な集客・信頼構築の鍵になります。
💬FAQ
比喩として使われている言葉なので、相手企業を名指しして断定的に批判する文脈では注意が必要です。 社内のディスカッションでは、「AIエージェントによる要約で、元サイトへの還元が少ない状態」といった 説明的な言い方を併用すると、誤解を避けやすくなります。
完全に把握するのは難しいですが、主要なAIサービスに対して自社のトピックやブランド名で質問し、 回答内に自社名やURLがどの程度登場しているかをチェックするのが現実的です。 また、自社名でウェブ検索した際に「AI回答」タブや要約表示がどうなっているかを見ることも一つの手段です。
自社のビジネスモデルやコンテンツの性質によって判断が分かれます。 報道や有料コンテンツなど、情報の正確性や収益構造への影響が大きい場合は制限を強める選択肢があります。 一方、ホワイトペーパーやナレッジ記事などは、要約されることで認知が広がるメリットもあるため、 コンテンツ単位でスタンスを分ける考え方もあります。
現時点では、従来の検索流入も依然として重要です。 AIエージェント対策は、SEOの代替ではなく「追加のレイヤー」と捉えるのが現実的です。 まずは、既存のSEO・コンテンツマーケティングをベースに、 「AIから見ても分かりやすい構造」と「ブランドが伝わる設計」を意識していくイメージが適しています。
技術的な詳細よりも、次の三点を軸に説明すると理解されやすくなります。
- 中長期的なオーガニック流入構造の変化(検索からAI回答へのシフト)
- コンテンツ投資とリターンの関係(どこまでAI利用を許容するか)
- ブランドとユーザー体験への影響(AI経由でどう見られるか)
そのうえで、具体的なニュース事例や、他社のポリシー公開例を共有すると、 社内での議論が進みやすくなります。
たとえば次のようなアクションから始めると、無理なく取り組みやすくなります。
- 主要なAIサービスで自社名検索をし、「どのように要約されているか」をスクリーンショットで共有する
- 自社コンテンツの中から、「AIに要約されても価値が伝わりやすい記事」「来訪してもらわないと価値が伝わりにくい記事」を分けて考えてみる
- 社内で簡易な方針メモ(AI利用に関するスタンスのドラフト)を作り、関係者とディスカッションする
こうした小さなステップでも、「AIエージェント前提の時代にどう向き合うか」という共通認識をつくる助けになります。
参考情報:Perplexityのクローリングやコンテンツ利用をめぐる議論や訴訟については、Cloudflare・TechCrunch・Reuters・各種報道・解説記事などが詳しく取り上げています。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。















-7-320x180.png)


-2025-11-17T173006.224.png)
-98-120x68.png)

-2025-11-17T150625.548-120x68.png)
-2025-11-17T162724.058-120x68.png)