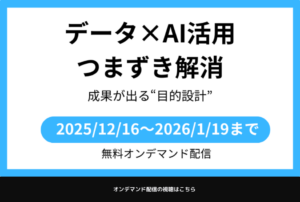ChatGPTやGoogleの「AIによる概要」に触れる機会が増え、私たちが情報を得る方法が根本的に変わりつつあることを、あなたも肌で感じているのではないでしょうか。ユーザーはもはやリンクをクリックするのではなく、AIに直接質問し、答えを得るようになっています。これは、これまでのオンラインでの認知度を高めるためのルールが、急速に時代遅れになっていることを意味します。
この記事の目的は、マーケターや事業者がこの新しい「アンサーエンジン」の時代で成功するために理解すべき、最も重要で、時に衝撃的ともいえる5つの変化を明らかにすることです。従来のSEOの考え方を捨て、これからのデジタル戦略を再構築するための戦略的指針として、ぜひ最後までお読みください。
「クリック」より「引用」が重要になる時代
SEO(検索エンジン最適化)からAEO(アンサーエンジン最適化)またはGEO(生成エンジン最適化)への根本的なシフトが起きています。PwCのような業界分析企業が指摘するように、これまでのSEOのゴールがウェブサイトへの「クリック」を獲得することだったのに対し、AEO/GEOのゴールは、あなたのコンテンツがAIの生成する回答の中に直接「引用」される、あるいは含まれることです。例えば、ユーザーが「ダラスで一番良い当座預金口座は?」とAIに尋ねた際、目指すべきは自社の銀行口座の詳細がAIの回答そのものに含まれることであり、単にサイトへのリンクが表示されることではありません。
なぜこれが重要なのでしょうか。ユーザーはリンクをクリックすることなく(ゼロクリック検索)、検索結果ページで直接答えを得るようになっています。この変化に対応できなければ、たとえ従来の検索順位が高くても、ブランドは顧客の目に触れる機会を失ってしまうかもしれません。ランキングを追いかける時代は終わりを告げ、AIにいかに信頼される情報源として認識されるかが問われています。
「特定の順位に執着する時代は終わりつつあります。」
AIは「ググる」のではなく「ウェブ全体」から学習する
AI時代の権威性は、従来の被リンクだけで構築されるわけではありません。AIはGoogleの検索順位が高いサイトだけを見ているのではなく、インターネット上に存在する膨大な情報源から総合的に学習しています。
ここで重要になるのが、従来の被リンクの概念を拡張する「ブランドメンション(言及)」と「共起(Co-citation)」です。AIは、クリック可能なリンクがなくても、ウェブ上であなたのブランドが言及されていること自体を権威のシグナルとして評価します。例えば、プロジェクト管理ツールを探しているユーザーに対し、AIが「Monday.comは、AsanaやClickUpと並んで人気のツールです」と回答する場合、Monday.comは強力な権威性シグナルを得ています。
さらに、AIは本物の会話が行われているプラットフォームの情報を重視する傾向があります。特に、RedditやYouTubeのようなユーザー生成コンテンツ(UGC)は、AIによる回答で頻繁に引用される情報源となっています。自社サイトの最適化だけでなく、こうした多様なプラットフォームでの存在感を高めることが、AIに「見つけてもらう」ための鍵となります。
顧客はAIに「買い物」を任せ始める
AI検索の進化は、単なる情報収集の変化にとどまりません。「エージェントコマース」という未来の購買行動がすぐそこまで来ています。これは、AIエージェントがユーザーに代わって商品を閲覧・比較し、購入手続きまでを自律的に実行する世界です。
例えば、あるユーザーがAIエージェントに「私が利用できる最高の小規模事業者向けローンを見つけて、申請を開始して」と指示したとします。AIは複数の銀行のシステムを解析し、金利や手数料、レビューを客観的に比較して最適な選択肢を提案し、申請プロセスまで進めるかもしれません。この過程では、銀行のウェブサイトや広告が完全にバイパスされる可能性があります。
これが突きつけるのは、単なる広告手法の変化ではなく、ブランド存続に関わる危機です。PwCが指摘するように、顧客が抱くブランドイメージは「AIが伝えた情報のみ」に基づいて形成されるかもしれず、企業が時間とコストをかけて構築したブランドストーリーや価値提案が、顧客の目に一切触れないという事態が起こり得ます。AIエージェントとのデータ連携ができない企業は、顧客の購買検討の選択肢から完全に姿を消してしまうリスクに直面しているのです。
成功の指標は「アクセス数」から「信頼性」へ
AIによるゼロクリック検索の増加に伴い、オーガニックトラフィックの量やキーワードランキングといった従来のKPIは、成功を測る絶対的な指標ではなくなりつつあります。これらはもはや成功の絶対的な指標ではなく、戦略の方向性を確認するための「参考指標」として扱うべきです。
この変化の背景には、ユーザーがサイトを訪れずとも答えを得られるようになったことがあります。コンサルティング企業ConductorのPatrick Reinhart氏が指摘するように、これからのマーケターは、トラフィックの量そのものよりも、その質やコンバージョンを重視するようになります。
「これにより、人々はトラフィック全般よりも、コンバージョンやトラフィックの質についてもっと考えるようになるでしょう。」
では、新たな指標とは何でしょうか。それは、AIの回答における「シェア・オブ・ボイス(言及の割合)」、ブランドが「引用された回数」、そしてE-E-A-T(Experience: 経験、Expertise: 専門性、Authority: 権威性、Trust: 信頼性)の実証です。AIはユーザーに信頼性の高い回答を提供することを目的とするため、これらの要素を実証しているコンテンツは、AIにとって信頼できる引用元となりやすく、結果として選ばれる可能性が高まります。そしてこの「信頼性」こそが、すでにAIを使い始めている消費者の行動を理解する鍵となります。
消費者もマーケターも、AIシフトの準備はできている
この変化は未来の話に聞こえるかもしれませんが、データは日本市場で消費者とマーケター双方がすでに対応を始めているという驚くべき現実を示しています。Criteo Japanの調査によると、消費者のAIに対する高い関心と、いまだ残る不信感との間に「信頼のギャップ」が存在しており、これこそが企業にとって最大の戦略的機会となっています。
消費者側では、AI活用への強い興味が見られます。しかし、そこには明確な課題も存在します。
• 消費者の6割以上がAIの活用に興味を持っています。
• AIからの提案を98%が受容しますが、約7割は公式サイトで情報を再確認する傾向にあり、AIの回答を鵜呑みにはしていません。
• 消費者がAIに最も期待するのは「商品の比較」(40.3%)と「パーソナライズされた提案」(37.5%)です。
一方、マーケター側の適応はさらに進んでいます。
• マーケターの実に9割近く(87%)がすでに業務でAIを活用しています。
• AIエージェントの活用意向も92%と非常に高い水準です。
このデータが示すのは、AIシフトが理論上の話ではなく、需要と供給の両面から駆動される現代のリアルな動きであるということです。そして、消費者が抱える「AIを信頼しきれない」というギャップを埋め、公式情報で最終確認される際の「信頼できる受け皿」になることこそが、この新しい時代で勝ち抜くための核心的な戦略なのです。
結論:最後に考えるべきこと
オンラインで「見つけてもらう」ためのルールは、キーワードの順位を競うゲームから、信頼され、引用される権威になるための挑戦へと変わりました。これは単なる戦術の変更ではなく、デジタルにおける存在意義そのものを問い直すパラダイムシフトです。
AIが情報の門番となる時代、あなたのブランドの声がただ聞こえるだけでなく、信頼され、推薦されるために、今何をすべきでしょうか?

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。











-7-320x180.png)






-72.png)
-25-120x68.png)
-24-120x68.png)
-71-120x68.png)
-73-120x68.png)