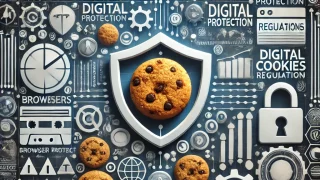リード獲得を刷新するAI×営業・マーケ戦略の最前線
BtoB企業のリード獲得を最適化するために、AIとデータ活用による営業・マーケ連携の実践事例と戦略を紹介します。
登壇者紹介
本ウェビナーには、AI活用やBtoBマーケティングの第一線で活躍する6名の登壇者が集結しました。
株式会社マイクロアド ダイレクトグロース部 第二営業局 局長の高乗悠樹氏は、BtoB向けアカウントプランナーとして100社以上の広告支援を経験し、現在は「シラレルリード獲得プラス」の推進に取り組んでいます。
株式会社インティメート・マージャー 代表取締役社長の簗島亮次氏は、DMP(データマネジメントプラットフォーム)領域の第一人者として、法人向けインテントデータの利活用に注力しています。
株式会社BizGenix 代表取締役の中山勇太郎氏は、営業とマーケティング双方の経験を持ち、事業成長に向けたマーケティング体制の構築支援を行っています。
株式会社To22 代表取締役 CEO の野間康平氏は、生成AIの業務実装支援を提供しています。
株式会社じげん 企画マーケティングUnit. Unit Head/求人事業部 Division Manager の西尾大笑氏は、SEOやカスタマージャーニー設計に精通し、事業部を横断したマーケティング支援を行っています。
エッジテクノロジー株式会社 AIプロダクト事業部 エヴァンジェリストの五十嵐政貴氏は、AIツール「Gene」を通じて営業自動化を推進しています。
セミナーの背景と問題意識
近年、BtoBマーケティングにおけるリード獲得施策は多様化・複雑化しており、「どこに注力すべきか」「有効なリードとは何か」など、企業が直面する課題は山積しています。本ウェビナーでは、こうした課題に対し、AIやデータドリブンな戦略を用いて成果を上げてきた企業が、具体的な施策や実践事例を共有しました。
キーメッセージと発言ハイライト
高乗氏は、過去の顧客データの定量・定性分析を通じて「LTVの高い顧客群」を明確にし、ターゲット層の戦略的な選定が必要であると強調しました。
全方位的な営業から脱却し、ターゲットごとに施策を最適化することが成果向上の鍵になります。(高乗氏)
西尾氏はカスタマージャーニーの設計において、「ペルソナの行動面の深掘り」が不可欠であると指摘しました。
単なる属性だけでなく、顧客の課題感や情報収集行動を踏まえた施策設計が必要です。(西尾氏)
野間氏は生成AIの活用方法について、「人間が苦手とする定性的なリストアップこそ、AIの活躍領域」と述べました。
例えば、中長期のビジョンを掲げている企業を自動抽出するなど、AIならではのリード探索が可能です。(野間氏)
実践的な取り組みと事例
マイクロアドでは、広告配信データと顧客情報を統合してマトリックス化し、業界・予算別にターゲット企業を分類。各群に対して施策を最適化した結果、
受注率はターゲット群で+9.7%、案件単価は3.2倍に改善しました。(高乗氏)
また、メタ広告への企業データ連携を通じて、CPAを削減しつつ商談化率を8%向上させた事例も紹介されました。エッジテクノロジーの五十嵐氏は、営業活動の自動化ツール「Gene」を紹介し、
従来の5倍のスピードでアプローチが可能になりました。(五十嵐氏)
To22の野間氏は、生成AIと人のハイブリッドで行うリサーチ業務の効率化事例を紹介し、
調査や資料作成にかかる時間が約2時間から5分に短縮されました。(野間氏)
今後の展望とまとめ
営業・マーケティングの連携強化や生成AIの活用は、BtoB企業にとってもはや必須のテーマです。登壇者たちは、今後は「量より質」、「汎用性より文脈適応性」のリード戦略が求められると強調しました。
有効リードの定義を共通化し、データやAIを“共通言語”として組織をつなげることが、次なる成果につながります。(簗島氏)
生成AIは叩き台を迅速に作成し、人間の目利きと補完によって精度を高める共創の時代に突入しました。データとAIを活用したリード獲得戦略は今後ますます進化していくでしょう。
読者の皆様も、まずは「何が自社の成果につながるのか」を見直すところから始め、AI活用を現場に組み込んでみてはいかがでしょうか。