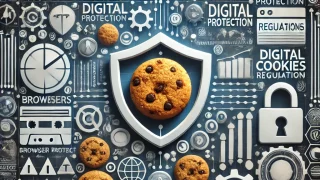ポストクッキー時代のデジタルマーケティング最前線 〜サードパーティクッキー規制撤廃後の企業の取り組み〜
ポストクッキー時代を見据えたデジタルマーケティングの最新動向と、企業の取り組み事例をご紹介します。クッキー規制の影響を受けつつも、新たなアプローチで成果を上げる方法論を探ります。
登壇者紹介
本セミナーには、デジタルマーケティングの第一線で活躍する4名の登壇者が集結しました。株式会社インティメート・マージャー代表取締役の簗島亮次氏は、アドテクノロジー領域のリーディングカンパニーとして、ポストクッキー時代のソリューション提供を牽引しています。株式会社イルグルム執行役員 マーケティングDX推進本部長の廣遥馬氏は、マーケティングのDX化を推進する立場から、最新のテクノロジーとデータ活用について豊富な知見を持っています。株式会社マイクロアド プロダクト戦略部シニアマネージャーの松本宗明氏は、アドプラットフォームの開発・運用を通じて、変化の激しい広告業界の最前線に立ち続けてきました。株式会社メディックス コンシューマーマーケティング推進ユニット長の當流谷圭氏は、消費者理解に基づくマーケティング戦略の立案・実行のプロフェッショナルです。
セミナーの背景と問題意識
デジタル広告を取り巻く環境が大きく変化する中で、特にサードパーティクッキーの規制が重要な転換点となっています。Googleは当初、Chromeにおけるサードパーティクッキーの廃止を予定していましたが、業界への影響を考慮し、規制の方針を見直しました。一方で、SafariやFirefoxではすでにサードパーティクッキーが制限されており、企業のデジタルマーケティングは新たな段階に入っています。
このような状況下で、企業はどのようにしてデータドリブンなマーケティングを進化させていくべきかが問われています。ポストクッキー時代に対応するためには、どのような選択肢やアプローチがあるのかが重要なテーマとなっています。本セミナーでは、こうした課題を踏まえ、最前線での取り組みについて意見交換が行われました。
キーメッセージと発言ハイライト
セミナーの中で特に強調されたのは、サードパーティクッキーに依存しないマーケティングへの移行が急務であるという点です。簗島氏は、現在のハイブリッドな環境では、クッキーが利用できるブラウザとそうでないブラウザの間でバランスを取ることが重要であると指摘しました。
クッキーが使えるブラウザ、使えないブラウザをバランスを取っていくっていうのがすごく今後のデジタルマーケティングにおいて重要かなと思います。(簗島氏)
また、ファーストパーティデータの活用や、コンテクストベースのターゲティングといった手法にも注目が集まっています。データを起点としたマーケティングの高度化は、ポストクッキー時代においても不可欠であり、ソリューション開発や、データに関する法整備の必要性についても言及されました。
実践的な取り組みと事例
株式会社インティメート・マージャーでは、ポストクッキー時代に対応したソリューション「IMUID」を開発し、クッキーが使えないブラウザでもターゲティング広告の配信を実現しています。簗島氏によると、このソリューションはすでに多くの企業で導入が進んでおり、リーチの拡大やCPA(顧客獲得単価)の改善といった成果も報告されています。
IMUIDを使ったPostCookieの配信の方が効果が出ているというお客様も結構増えてきています。(簗島氏)
さらに、Criteoとのデータ連携により、クッキーが使えない環境においてもダイナミッククリエイティブ広告の配信が可能となり、広告の最適化によって売上の向上にもつながっているとのことです。
また、インティメート・マージャーでは、自社のDMP(データマネジメントプラットフォーム)とAIを組み合わせて、サイト訪問者の特性を可視化しています。これにより、クッキーが利用できない状況でも顧客像の理解を深め、マーケティング施策の立案に役立てているといいます。
今後の展望とまとめ
本セミナーを通じて明らかになったのは、ポストクッキー時代に求められるマーケティングのアプローチが多様化しているという点です。サードパーティクッキー以外の識別子やコンテクスト情報を活用しながら、マーケティングの高度化を進める必要があります。加えて、ファーストパーティデータの戦略的な収集と活用、そしてプライバシーに配慮したデータガバナンスの確立も重要な課題として認識されました。
技術的なソリューションを導入するだけでなく、データ活用に向けた組織体制を整えることが、デジタルシフトを加速させる鍵となります。ポストクッキー領域はまだ未開拓の分野が多く、積極的に挑戦することで競争優位性を築くことも可能です。企業には、変化を的確に捉え、新しい価値を創出するための取り組みが求められています。